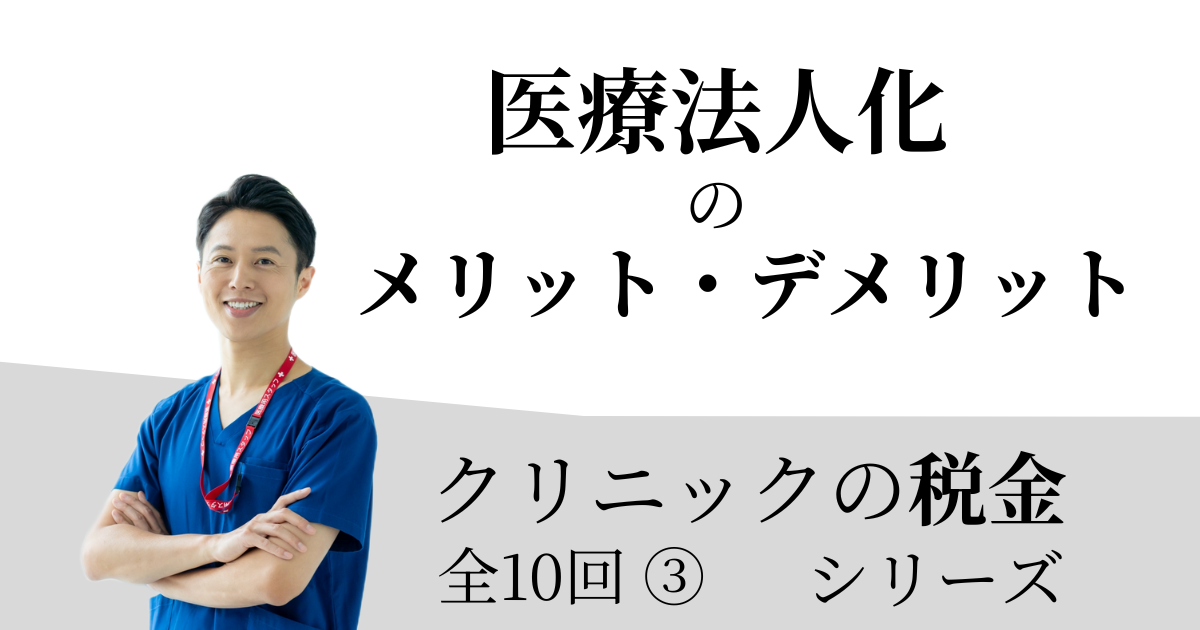クリニック経営が安定し、利益が積み上がってくると、多くの院長先生が「法人化」を検討されます。個人事業のままか、医療法人とするか。この選択は税負担だけでなく、ライフプランや承継設計にも直結します。
本記事では税制の観点から法人化のメリット・デメリットを整理し、3つの所得水準を例に具体的なシミュレーションを示します。
クリニックの税金 ➂|医療法人化のメリット・デメリット
1. 税率の違いによる節税効果
個人開業医は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります。最高で55%に達する場合もあります。法人税は概ね23%前後に抑えられるため、規模が大きくなるほど法人化の効果は顕著になります。
シミュレーション① 年間所得2,400万円(月200万円)
- 個人事業:税負担 約900万円(実効税率38%)
- 医療法人:法人税 約480万円(実効税率20%)
→ 差額は約420万円。ただし、社会保険料や顧問料で吸収されやすく、微妙な水準。
シミュレーション② 年間所得5,000万円(月410万円)
- 個人事業:税負担 約2,400万円(実効税率48%)
- 医療法人:法人税 約1,150万円(実効税率23%)
→ 差額は約1,250万円。多くの医院で「法人化しなければ資金が残らない」と実感されるレンジ。
シミュレーション③ 年間所得1億円(月830万円)
- 個人事業:税負担 約4,800万円(実効税率48%)
- 医療法人:法人税 約2,300万円(実効税率23%)
→ 差額は約2,500万円。役員報酬・退職金制度・所得分散を駆使すれば、さらに節税効果が広がる。
2. 役員報酬による所得分散
医療法人化の大きな特徴は、院長が法人から「役員報酬」として給与を受け取る点にあります。これにより、法人側に残す利益と院長個人に帰属させる所得を調整でき、税率をコントロールする余地が生まれます。さらに、配偶者や後継者を役員に登用して報酬を分散すれば、累進課税の影響を抑え、家庭全体での税負担を下げることが可能です。
- 法人側に利益を残せば法人税率(約23%)で課税
- 院長は給与として受け取り、累進課税を調整可能
- 配偶者・後継者に役員報酬を分散し節税
- 所得分散は承継準備にも直結
例として、院長1人で2,000万円を受け取ると最高税率帯になりますが、夫婦で1,000万円ずつ分ければ、合計の税額は数百万円単位で軽減される場合があります。節税と承継を同時に進められるのは法人化ならではの強みです。
3. 経費範囲の拡大
法人化することで、経費として認められる範囲が広がり、資金繰りの柔軟性が増します。特に役員退職金制度を整えると、多額の退職金を損金として計上でき、法人税の圧縮効果が非常に大きくなります。
同時に、受け取る個人は退職所得控除や2分の1課税を利用できるため、老後資金の準備としても有効です。その他、福利厚生費や規程に基づく出張費など、個人では難しい経費も法人であれば認められる余地があります。
- 役員退職金制度で大幅な損金算入が可能
- 個人側は退職所得控除で税負担軽減
- 福利厚生費の計上範囲が拡大
- 規程化した出張費・会議費も認められやすい
例えば退職金3,000万円を法人経費に計上すれば、法人税を数百万円規模で抑えられます。個人も有利な税制で受け取れるため、「節税と老後資金確保の両立」が可能です。長期的視点で制度設計することが重要です。
4. 相続・承継の容易さ
個人開業医の場合、医院の建物・医療機器・預金はすべて院長個人の財産とされ、相続時には課税対象となります。これにより相続税が高額となり、承継が難航するケースも少なくありません。
医療法人に移行すれば、医院の資産は法人の所有物となり、相続財産から外れるため課税対象が縮小します。さらに法人格をそのまま承継できるため、患者さんやスタッフへの影響を最小化し、円滑な承継が可能です。
- 法人所有の資産は相続財産から除外
- 相続税の課税対象が縮小し負担軽減
- 後継者を理事長に据えるだけで承継可能
- M&Aやグループ化にも活用しやすい
法人化は「税金対策」だけでなく「医院の未来」を見据えた選択です。承継リスクを減らし、スムーズに世代交代を実現できる点は大きな利点です。組織としての持続性を高めたい医院にとって有効な基盤となります。
5.法人化のデメリット・注意点
医療法人化には明確なメリットがある一方で、見逃せないデメリットも存在します。設立や運営にはコストがかかり、資金の使い方も「法人のお金」と「個人の報酬」が明確に分かれます。さらに社会保険料の負担増や、解散時に残余財産を出資者へ戻せない制約など、個人開業時にはなかった制限が生じます。こうした点を把握せずに法人化すると、かえって負担が増すこともあるため、事前に十分な検討が必要です。
- 設立・運営コスト
設立時に100万円前後、さらに決算・税務・社保の顧問料が毎月数万円単位で発生。 - 資金の自由度が下がる
法人の利益は「院長の財布」ではなく、給与や役員報酬として受け取る必要がある。 - 社会保険料の増加
厚生年金・健康保険への加入義務で、年間数百万円の負担増となるケースも。 - 解散時の制約
医療法人は株式会社と違い、解散時の残余財産を出資者が受け取れない。
6.判断の目安
法人化の是非は、医院の所得規模によって大きく変わります。年間所得が2,400万円程度であれば、節税メリットは限定的で、社会保険料や顧問料の増加に吸収されやすいため無理に法人化する必要はありません。
5,000万円規模に達すると、税負担の差が毎年1,000万円を超えることもあり、承継準備や資金繰り改善の観点からも法人化を本格的に検討すべき水準となります。
そして1億円規模になれば、節税効果だけでなく承継対策や資産管理の面からも法人化は必須です。
年商2,400万円(約月200万円)
→ 節税効果は限定的。社会保険料や顧問料でほぼ相殺。
この水準では無理に法人化せず、将来の成長を見て判断で十分。
年商5,000万円(約月410万円)
→ 法人化のメリットが明確。節税額が毎年1,000万円規模に達し、承継対策の観点からも現実的。
この水準に入ったら、法人化を真剣に検討すべきタイミング。
年商1億円(月830万円)
→ 法人化はほぼ必須。税制面・承継面のリスクが大きすぎ、法人化を避ける理由はない。

まとめ
医療法人化は、所得水準によってメリットの大きさが変わります。年間所得2,400万円前後では表面的な税負担は下がるものの、社会保険料や顧問料で吸収されやすく、慎重な判断が必要です。
一方で、5,000万円前後になると税負担の差が毎年1,000万円を超えることもあり、多くのクリニックにとって法人化は現実的な選択肢となります。さらに1億円規模では、資金繰りや承継リスクを考えても法人化はほぼ必須といえます。
重要なのは、単なる節税額だけで判断せず、ライフプランや承継戦略を含めた長期的な医院経営の視点から検討することです。法人化は「いつ行うか」が最も重要であり、信頼できる専門家と複数のシミュレーションを行い、自院に最も適した時期を見極めることが成功の鍵となります。
※消費税の取扱いは改正や解釈変更が随時行われます。必ず顧問税理士にご確認ください。
【無料】75%公開版チェックリストをご提供中
本シリーズでは、クリニック経営に欠かせない考え方や仕組みを整理して解説しています。
その次の一歩として、経営全体を体系的に把握できる「BSC(バランス・スコアカード)75%公開版チェックリスト」を無料でご提供しています。
数値だけに偏らない経営課題の整理や、スタッフと共有できる指標づくりの土台としてぜひご活用ください。
ご希望の方は、下記より資料請求または無料相談にお進みください。
▶BSC(バランススコアカード)については、こちらのまとめからご覧ください。
▶ 「経営戦略」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます