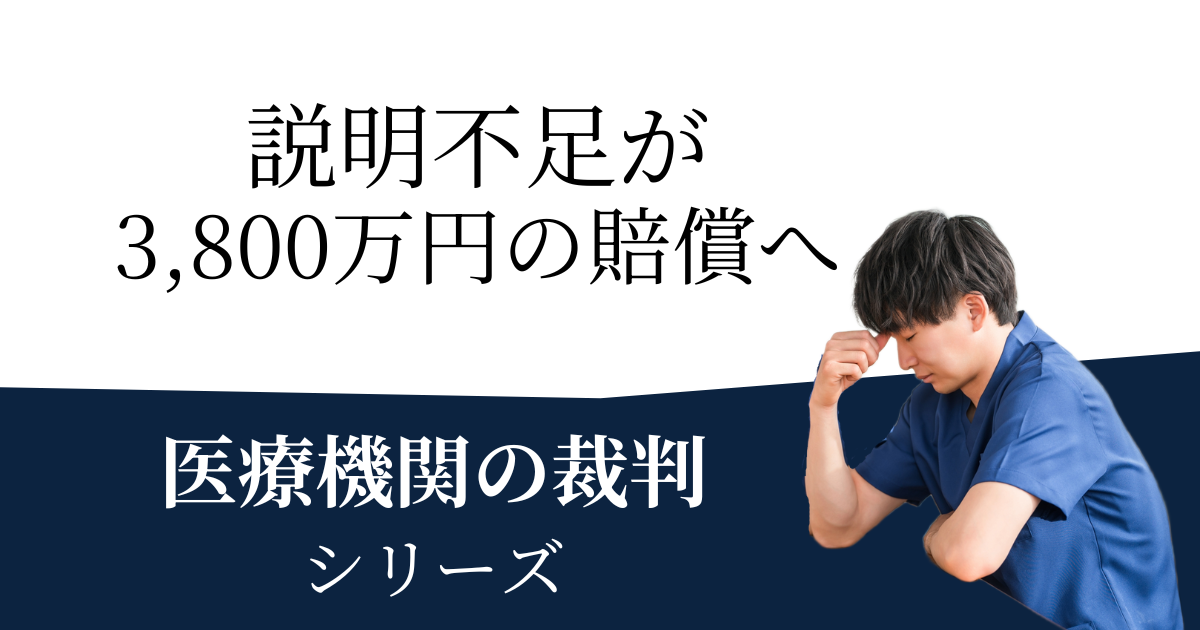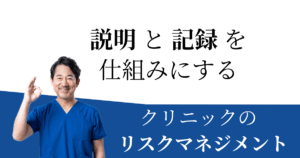医療機関にとって「裁判」は遠い存在のように思われがちです。しかし実際には、日常の診療から裁判に発展するリスクは誰にでも起こり得ます。しかも、必ずしも医療過誤そのものが争点になるとは限りません。治療そのものは適切に行われていたにもかかわらず、「説明不足」や「記録不備」といった管理上の小さな落とし穴が、数千万円規模の賠償に結びつくことがあります。
本記事では、首都圏の歯科医院で2010年代前半に起きた実際の判例を紹介します。治療内容そのものよりも「説明義務違反」が争点となり、約3,800万円の賠償命令が下された衝撃的な事例です。
医療機関の裁判シリーズ:説明不足が3,800万円の賠償へ
判例の概要
舞台は首都圏にある中規模の歯科医院。患者は40代の男性で、長年の咬合不全を改善するためインプラント治療を希望しました。手術は2012年に実施され、インプラント体の埋入自体は問題なく成功。しかし、術後しばらくして患者に下唇のしびれが残る神経麻痺の症状が出現しました。
患者側は「術前に神経麻痺のリスクについて十分な説明を受けていなかった」と主張。訴訟は東京地裁で審理され、2014年に判決が言い渡されました。
- 医師は「術前に口頭で説明した」と証言したが、その記録はカルテにも残されていなかった
- 患者は「説明を受けた覚えはない」と一貫して主張
- 裁判所は「医師側の説明義務は果たされていなかった」と判断し、3,800万円の損害賠償を命じた
ここで注目すべきは、手術そのものに重大な過失は認められなかった点です。つまり、医学的な技術ではなく、「説明」と「記録」の不備が訴訟の核心だったのです。
判決から読み取れる教訓
記録の徹底が最大の防御策
口頭でどれだけ丁寧に説明しても、証拠として残っていなければ法廷では意味を持ちません。
同意書への署名だけでなく、「リスクを説明した日時」「使用資料」「患者の反応」までカルテに具体的に記録する必要があります。
患者の理解度確認の重要性
説明は医師の自己満足で終わってはなりません。
患者が理解できる言葉を使い、図解や模型を用い、「理解できたかどうか」を確認する一言を必ず添えましょう。
今回のケースでは、患者が「そんな話は聞いていない」と言った時点で、医師側には証拠がなく反論できませんでした。
自由診療のリスクの高さ
インプラントや美容医療など、高額な自由診療は患者の期待値が高く、結果への不満が訴訟へ直結しやすい傾向があります。
自由診療を扱う医療機関は、説明義務を「過剰なくらい」徹底する必要があります。
経営へのインパクト
この判例が示すのは「一枚の説明記録の有無が、数千万円の損害に直結する」という厳しい現実です。賠償金だけでなく、裁判沙汰になったという事実はインターネットや口コミを通じて広まり、経営に甚大な影響を及ぼします。
- 経済的損失:賠償金に加え、弁護士費用や裁判対応に伴う人件費が発生
- 風評被害:地域での評判が一気に下がり、新規患者が激減
- スタッフ士気の低下:職場の空気が重くなり、離職につながることもある
これらはすべて「経営リスク」として院長が背負うことになります。
医療機関が取るべき対応策
苦情を正しく処理する姿勢自体が、訴訟リスクを大幅に下げます
説明プロセスの標準化
手術や処置ごとに「説明用チェックリスト」を作成し、必ず説明した項目にチェックを入れる
チェックリストを同意書と一緒に保管することで証拠力を強化
スタッフ教育の徹底
医師だけでなく、受付や歯科衛生士も患者説明に関与する場面があります
「誰が・いつ・何を説明したか」を全スタッフが意識する文化を作ることが大切です
苦情対応マニュアルの整備
苦情は放置せず、記録に残して対応することでトラブル拡大を防ぐ
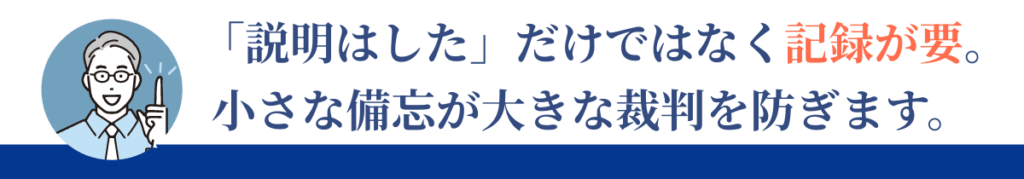
まとめ
今回紹介した判例は、医療行為そのものの過誤ではなく「説明不足」が裁判の焦点となった衝撃的なケースでした。医療機関にとって学ぶべきは、日常の小さな説明・記録が、数千万円規模のリスクを回避するということです。
「治療がうまくいっているから大丈夫」ではなく、「説明と記録を徹底しているから大丈夫」と胸を張れる組織づくりが、これからの医療機関には求められます。
▶どうすれば良いか?は対応するリスクマネジメントの記事を見る
▶医療機関の裁判シリーズ:まとめに戻る
無料リソースのご案内
日常の診療から経営リスクを遠ざけるためには、「組織力の強化」と「仕組みの整備」が欠かせません。
当社では、医院の現状を客観的に把握できる
「BSCチェックリスト(75%公開版)」 を無料でご提供しています。
下記ボタンよりぜひご請求いただき、
自院のリスクマネジメントと組織づくりにご活用ください。。
▶ 「組織づくり」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます