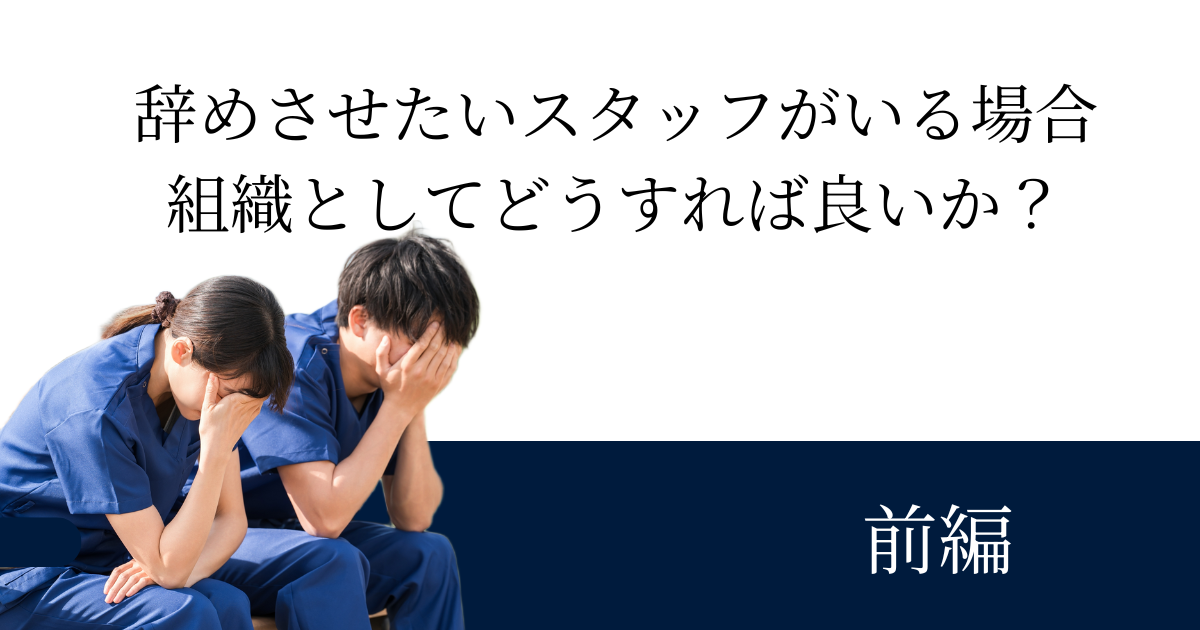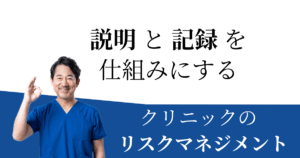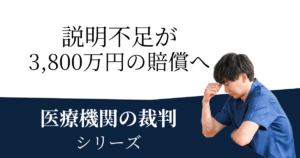〜注意しても直らない、でも辞めないスタッフにどう向き合うか〜
辞めさせたいスタッフがいる場合、組織としてどうすれば良いか?【前編】
「いるだけで悪影響…でも辞めようとしない」悩ましい存在
「院長や他のスタッフの悪口を平然と言う」
「指示に納得できないからやりません、と拒否する」
「和を乱しているのに、なぜか辞めようとしない」
クリニックにおいて、こうしたスタッフの存在に頭を悩ませている院長やリーダーの方は少なくありません。
一見すると強気で自己主張が強く、本人なりの“正義”に基づいて行動しているように見える。
しかし実際には、周囲の信頼を失い、チームの空気を悪くしている要因になっているのです。
なぜ、こういうスタッフが辞めようとしないのか?
こうしたスタッフは、しばしば次のような特徴を持っています。
- 注意をしても聞き流す、あるいは逆ギレする
- 周囲からのフィードバックを受け取ろうとしない
- 自分の居場所があると思い込んでいる
- 「ここにいれば安心」という勘違いをしている
つまり、本人には問題意識がまったくないのです。
そして「本気で叱られることもないし、自分は必要とされている」と思っている場合すらあります。
“注意する”だけでは、何も変わらない
何度も注意しているのに改善しないーーその背景には、
注意が「その場しのぎ」で終わっていたり、行動変化につながる仕組みがないことが多いのです。
- 指摘だけして終わっていないか?
- フィードバックを“記録”に残しているか?
- 他スタッフとの関係性を可視化できているか?
こうした整理ができていないと、いくら注意しても本人は「大したことではない」と受け止めてしまいます。
組織として「ルールと見える化」が必要
重要なのは、個人対個人の問題として扱わないことです。
院長 vs 問題スタッフ という構図になると、どんなに正論を伝えても、
「院長に嫌われてるだけだ」「私は標的にされている」といった被害者意識につながりやすくなります。
だからこそ、組織として
- 行動基準を明文化(接遇5原則・行動指針など)
- 評価やフィードバックを“見える化”(BSCやサーベイなど)
- 定期面談での記録を残す
といった“透明な基準”と“構造”を整えることが不可欠です。
「本人が気づいていない」ことへの対処法
このタイプのスタッフは、「自分が嫌われている」「周りから浮いている」ことに気づいていないことがほとんどです。
そのため、いくら論理で説明しても通じません。
有効なのは、
- 第三者によるフィードバック(サーベイなど)
- 言葉ではなく「データ」で現状を伝える
- 一対一で感情的にならずに向き合う
ことです。
「あなただけが感じているのではなく、組織全体がこう受け止めている」という構図に変えることが、本人の思い込みに揺さぶりをかける第一歩となります。
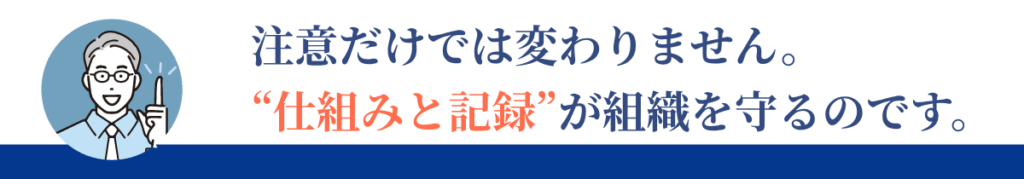
■前編まとめ:「個人対応」ではなく「組織対応」が鍵
辞めさせたいと感じるスタッフに対しては、
感情的になったり、個人間の対立に陥るのではなく、組織としての“基準と体制”で対応する姿勢が大切です。
そのうえで、後編では実際に「辞めてもらう」までの判断とプロセスについて具体的に解説します。
▶「やめさせたいスタッフがいる場合、組織としてどうすれば良いか」シリーズまとめに戻る
無料リソースのご案内
評価制度やキャリア設計の見直しをお考えの医院には、
接遇5原則チェックシートや「BSCチェックリスト(75%公開版)」を無料提供しております。
ぜひ下記からご活用ください。
▶ 「組織づくり」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます