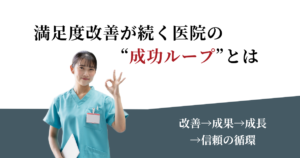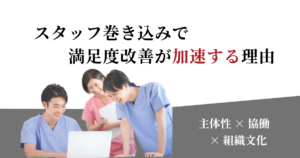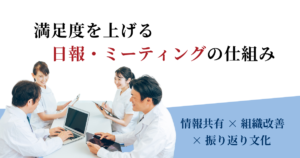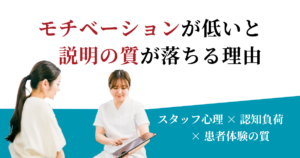患者満足度が高い医院に共通する、たった3つの視点とは?
「患者満足を上げたい」と考える院長は多い一方で、
満足度を“どう定義し、どう高めるか”については曖昧なまま取り組まれているケースが少なくありません。
私たちはこれまで多くのクリニックに関わる中で、
患者満足度が高い医院には共通する「3つの視点」があることに気づきました。
それは、表面的なサービスの質ではなく、医院全体の意識と設計の方向性に関わるものです。
1. 「患者さんが何を求めて来院しているか」を常に見失わない
まず大前提として、患者は「治療を受けに来ている」のではなく、
“不安の解消”や“安心感の獲得”を求めて来院しているという視点を持つことが欠かせません。
もちろん、治療や処置は大切ですが、
それがどれだけ高い技術であっても「安心できなかった」「不安が残った」では満足度にはつながりません。
満足度の高い医院では、次のような言葉がよくスタッフから聞かれます。
「○○さん、今日は大丈夫そうですか?」
「前回の麻酔、気になっていたのですが問題なさそうですか?」
こうした“心を汲み取る視点”が、日々の対応に自然と現れています。
患者の行動や言葉の背景にある「感情」に目を向けていることが大きな違いです。
2. 満足度の定義が“具体的に共有されている”
次に重要なのは、「満足度とは何か」という定義が院長とスタッフの間で言語化・共有されているかという点です。
よくある誤解は、スタッフが「満足=笑顔で対応」「丁寧な言葉遣い」など、接遇の一部分に限定して考えてしまっていることです。
もちろんそれらは大切な要素ですが、患者満足は以下のような要素の総和で決まります:
- 診療内容に対する納得感
- 待ち時間や予約のスムーズさ
- スタッフの対応
- 医院の清潔感や雰囲気
- 説明の分かりやすさとタイミング
これらがバラバラに運用されている医院では、たとえ部分的に良くても患者満足は伸び悩みます。
満足度の高い医院では、これらの要素をスタッフ向けに明文化したチェックリストや方針資料として共有しており、
「どこに注力すればいいか」が全員にとって明確になっています。
3. 数字とフィードバックを“仕組み”として取り入れている
最後の視点は、満足度を感覚ではなく“仕組み”として運用しているかどうかです。
感覚的に「最近クレームが少ないから満足度は高いはず」と考えていると、
思わぬリスクに気づけず、離反や悪評につながることがあります。
満足度の高い医院では、患者アンケートやNPS(ネット・プロモーター・スコア)などの定量指標を定期的に取得し、
定期的に院内で共有・改善に活用しています。
たとえば、私たちが提供している「E-Pサーベイ」では、
医院ごとのニーズに合わせたアンケートを簡単に作成でき、
NPS(=「この医院を他人に勧めたいと思うか」)も自動集計されます。
このように、満足度を測定→分析→改善というサイクルで運用している医院では、
小さな不満を早期にキャッチし、結果的に大きな満足と定着率向上につながっています。
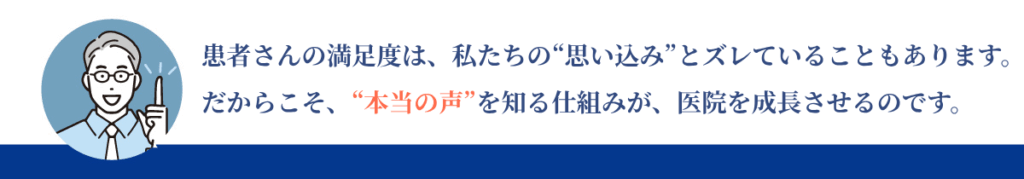
終わりに──患者満足度は“文化”として育てていくもの
患者満足は「取り組んだらすぐ上がるもの」ではなく、
理念に基づき、仕組みとスタッフ行動が連動して初めて育っていくものです。
そして、数字やフィードバックは、その「文化」が機能しているかを測るための鏡です。
まずは、自院の“今の声”を知ることから始めてみませんか?
E-Pサーベイなら、半年間無料で満足度調査をスタートできます。
下記からエントリー可能です。
▶ 「組織づくり」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます