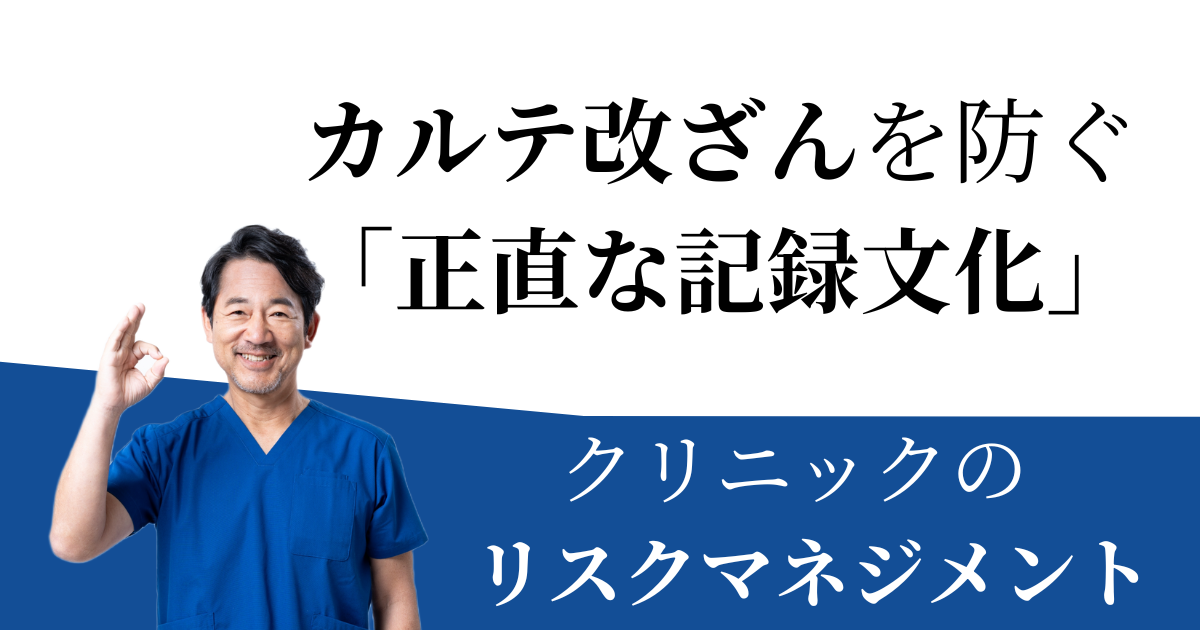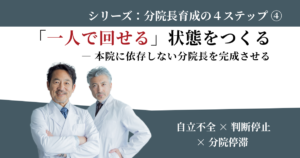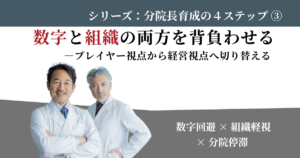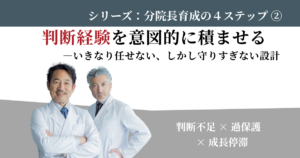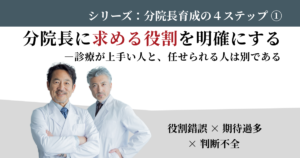カルテは医療行為を記録するためだけのものではありません。診療経過を裏付ける「証拠」であり、同時に患者の権利を守る重要な資料でもあります。
もしカルテが改ざんされれば、その信頼性は一瞬で崩れ去り、医療機関全体の信用を揺るがすことになります。実際、過去にはカルテ改ざんをめぐって最高裁まで争われた事件が存在し、診療の過失以上に「不誠実さ」が裁判所から厳しく断罪されました。結果は数百万円から数千万円規模の賠償命令と、取り返しのつかない信頼の失墜です。
本記事では、経営者が知っておくべきカルテ改ざんリスクの本質と、その防止策について具体的に解説します。
クリニックのリスクマネジメントシリーズ:カルテ改ざんを防ぐ「正直な記録文化」
リスクの本質
カルテ改ざんは単なる書類不備にとどまらず、医療の信頼基盤を根底から揺るがす行為です。カルテは患者に対する説明責任を果たす資料であり、治療の妥当性を示す客観的証拠でもあります。
これを操作することは患者さんの自己決定権を奪い、医療行為の是非を超えて「誠実さ」の欠如として裁かれます。過去の判例でも診療過誤がなくても、改ざん自体が厳しく非難され、病院の責任が重く問われました。
- カルテ改ざんは「信頼の破壊行為」と認識される
- 裁判所は医療技術より「誠実さ」を重視
- 過失がなくても改ざんで敗訴に至る可能性
- 経営者にとって存続を左右する重大リスク
カルテ改ざんは「診療の巧拙」ではなく「誠実さ」の問題です。どんなに高度な医療を提供しても、記録を失えば医院は一夜にして信頼を失墜し、経営危機に直結します。
経営への影響
カルテ改ざんが発覚すれば、判決で賠償命令を受けることはもちろん、経営全体への影響は金額を超えて深刻です。数百万円から数千万円規模の賠償は直接的負担ですが、最大の問題は「信用の失墜」です。
信頼を失えば新規患者の来院は激減し、既存患者も離脱します。報道による拡散で医院名は広く知れ渡り、スタッフの誇りやモチベーションも失われます。長期的にはブランド価値を取り戻すことが困難になり、存続すら危ぶまれます。
- 損害賠償額は数百万円~数千万円に及ぶ
- 信用喪失は新患獲得と既存患者維持に直撃
- 報道で医院名が拡散し社会的非難を浴びる
- スタッフの士気低下・離職連鎖で内部崩壊
カルテ改ざんの影響は「金額」以上に「信頼の喪失」です。患者・スタッフ・社会からの信頼が失われれば、医院のブランドは崩壊し、経営再建に膨大な時間と費用を要することになります。
実践すべき対応策
1. 電子カルテの管理強化
現代の医療現場では電子カルテが主流です。電子化のメリットは「修正履歴を残せる」ことにあります。誰が、いつ、どの部分を修正したのかログを自動的に記録し、改ざんを事実上不可能にする仕組みを整えることが第一歩です。アクセス権限を制限し、必要のない職員がデータに触れられないようにすることも欠かせません。
2. 訂正ルールの標準化
誤記や記載ミスは避けられません。重要なのは「正しく訂正する手順」を組織として統一することです。紙カルテであれば二重線で訂正し、訂正理由と署名を残す。電子カルテであれば履歴機能を活用する。これらをマニュアル化し、誰が対応しても同じ水準で訂正が行える体制を作ることが大切です。
3. 職員教育の徹底
カルテ改ざんは「禁止」と言葉で伝えるだけでは不十分です。なぜ改ざんがリスクなのか、判例でどのような結末を迎えたのかを具体的に教育し、職員一人ひとりに当事者意識を持たせる必要があります。新人研修や定期的な勉強会に「記録の重要性」を組み込むことで、改ざん防止は組織文化として根づきます。
4. 外部チェックと第三者認証
内部ルールだけでは不十分なこともあります。外部の監査やコンサルタントを定期的に活用し、記録管理体制をチェックすることが有効です。さらに、第三者認証を取得することで「外部から見ても透明性が担保されている」ことを証明できます。GVでは、こうした観点から JAPHICマークメディカル の取得を推奨しています。情報管理における第三者認証は、患者や取引先に対する信頼の証となります。
▶第三者認証マーク「JAPHICマークメディカル」についてはこちら
5. 「正直な記録文化」の醸成
最終的には仕組みだけでなく、組織文化が重要です。カルテは患者さんの権利を守るものであり、誤りがあった場合も「正直に残す」ことが医療機関の信頼を守る最良の方法です。院長や経営層が率先して「隠さない文化」を体現し、日常の中で透明性を意識させることが、最大のリスクマネジメントとなります。

まとめ
カルテ改ざん事件は、診療の過失ではなく「誠実さ」が厳しく問われた判例でした。賠償額は数百万円から数千万円に及び、病院は経済的損失と社会的非難という二重の打撃を受けました。この事例が示す教訓は明確です。「記録の信頼性は経営の生命線」 であるということです。
経営者は「記録は後から触らない」「訂正は正しい手順で残す」「外部からも透明性を証明する」という3つの原則を徹底すべきです。そして、組織全体に「正直な記録文化」を根づかせることが、患者と医院を守り、継続的な発展を可能にする最大の防御策です。
▶クリニックのリスクマネジメントシリーズ:まとめページに戻る
無料リソースのご案内
組織力を強化し、医院の成長を加速させたいとお考えの院長へ。
経営の現状と改善ポイントを客観的に把握できる「BSCチェックリスト(75%公開版)」を無料でご提供しています。
ぜひ下記ボタンより請求し、自院の組織づくりにお役立てください。
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます