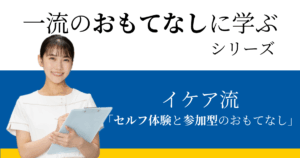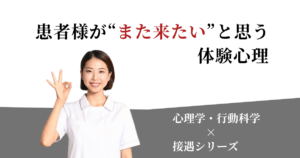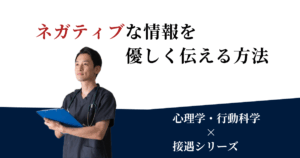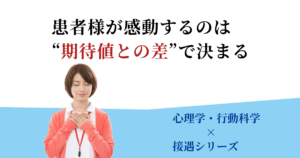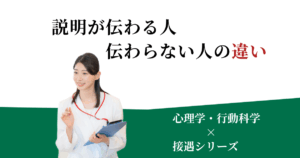医院の電話対応は、患者さんにとって「最初の印象」を決める重要な接点です。しかしスタッフごとに対応の仕方や声のトーン、言い回しが異なると、医院としての統一感が失われ、「対応がバラバラ」「説明が毎回違う」といった不信感につながることがあります。
電話対応は単なる事務作業ではなく、医院の信頼を支える大切な接遇です。
本記事では、スタッフごとの差をなくし、安心感と統一感のある電話対応を実現するためのポイントをご紹介します。
スタッフごとに電話対応が違うときの統一方法
対応のバラつきが生まれる理由
電話対応は、マニュアル化が難しい業務のひとつです。相手の状況や会話の流れに応じて言葉を選ぶ必要があり、経験や個人の会話習慣によって差が出やすくなります。まずは「なぜ統一が崩れるのか」を理解することが改善の第一歩です。
● 「自分なりの対応」がそのままクセになっている
● 忙しい時ほど言葉遣いが乱れやすい
● マニュアルがあるが活用されていない
● 新人とベテランで会話の型が違う
● 接遇への意識に温度差がある
放置すると、患者さんは「電話のたびに印象が違う医院」と感じてしまいます。
統一の第一歩は「共通フレーズ」を決めること
全員が同じ印象を与えるために、まずは言葉の型をつくることが大切です。細部をすべて揃えようとするのではなく、「核となるフレーズ」を共通化するだけでも、統一感は格段に高まります。
● 「お電話ありがとうございます。〇〇クリニックです」
● 「確認いたしますので、少々お待ちくださいませ」
● 「お待たせいたしました。お電話変わりました」
● 「ほかにご不明な点はございますか?」
このような基本フレーズが医院の“声のブランド”になります。
現場で自然に使える仕組みづくり
マニュアルは作って終わりではありません。実際に現場で使われるためには、「覚えやすく」「口に出しやすく」「共有しやすい」形にする必要があります。
声に出して読み合わせることで、自然な統一感が育ちます。また、実際の電話対応を録音・振り返り練習に活用することで、意識や改善ポイントが見える化され、日常の対応に定着しやすくなります。「使えるマニュアル」は現場で育てるものです。
電話対応を統一するための実践ポイント
現場の忙しさや個人差を踏まえつつ、誰でも実践しやすい方法をまとめました。決して「全員同じ話し方にする」ことが目的ではなく、医院としての信頼感を作ることがゴールです。
● まずは「はじめの挨拶」と「終わりの言葉」を統一
● 全員でロールプレイを実施し、声とトーンも確認
● よくある質問への対応は“共通回答メモ”を作成
● 新人スタッフには音声サンプルで学んでもらう
● 月に1度、電話対応の振り返りを行う
トレーニングは短時間でも継続が鍵です。
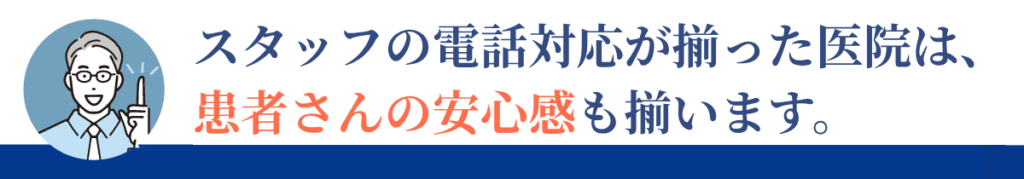
まとめ
スタッフごとに対応が異なると、患者さんは「対応品質にばらつきがある医院」と感じてしまいます。しかし共通フレーズを決め、全員で声を合わせる習慣を作ることで、医院全体としての一体感と信頼感が高まります。
電話対応は、医院の印象を決定づける接遇の最前線です。少しの工夫で「安心して任せられる医院」を実現できます。
なお、もし統一に課題を感じている場合は、
GVの接遇研修(3up Project) で実践的なロールプレイやトレーニングをご提供しております。
スタッフの「声」と「対応力」を整えたい医院様に最適です。
患者対応はまず【基本】を押さえることが大切です
▶接遇5原則 チェックシート活用法(全3回)を見る
▶電話対応 基本から応用/極意まで(全3回)を見る
無料サービスのご案内
接遇の質を見直すことは、患者さんとの信頼関係をより強くする第一歩です。
当社では 「接遇5原則チェックシート」 を無料でご提供しており、日々の接遇改善にすぐ活用いただけます。
さらに、接遇研修や満足度調査「E-Pサーベイ」のご相談も承っています。お気軽にご相談ください。
ぜひ下記からご請求ください。
▶ 「接遇・ホスピタリティ」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます