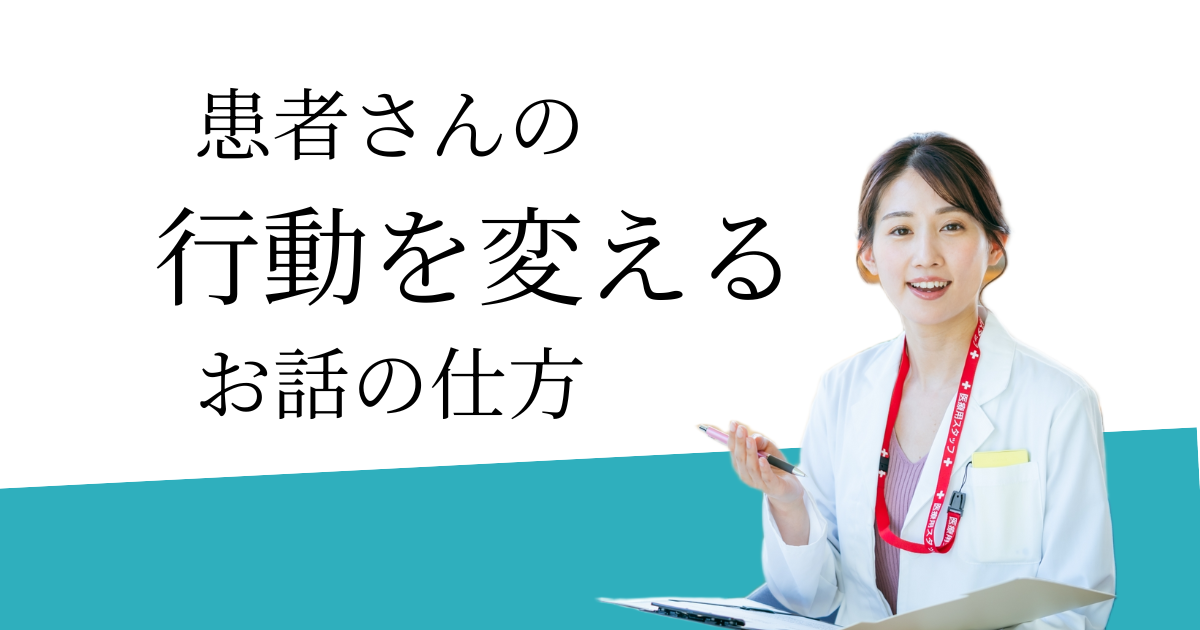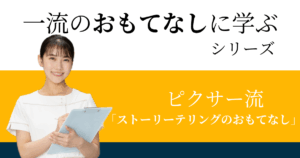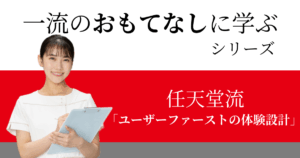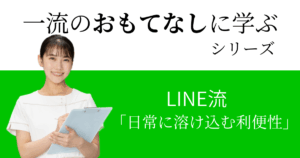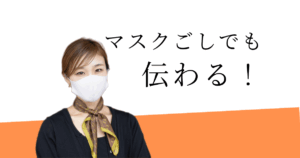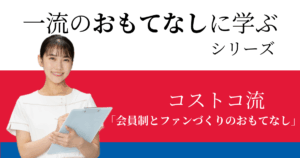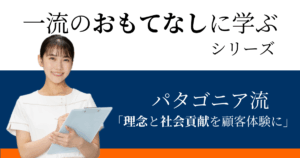医療の現場では、患者さんに薬の服用や生活習慣の改善をお願いしても、なかなか行動に移してもらえないことがよくあります。
特に慢性疾患や予防医療では、患者さんが日常生活の中で継続的に行動を変えることが不可欠です。そのために重要なのが、単なる説明や指示ではなく、患者さんが自ら「やってみよう」と思えるような話し方です。
本稿では、患者さんの行動を変えるための実践的なコミュニケーションのポイントをお伝えします。
患者さんの行動を変える お話の仕方
信頼関係を土台にする
行動変容は信頼関係なしには成り立ちません。
患者さんは信頼していない医療者からの指示に従おうとはしません。診察室に入った瞬間から目を見て挨拶し、話を最後まで聴く姿勢を持つことが大切です。
- 患者さんの話を途中で遮らない
- 小さな相槌や笑顔で安心感を与える
- プライバシーに配慮した環境で話す
こうした行動の積み重ねが「この人の言うことならやってみよう」という気持ちを引き出します。
なぜ必要かを先に伝える
指示を出す前に、「なぜその行動が必要なのか」を明確にしましょう。
例:「この薬を毎日飲むことで血圧が安定し、将来の脳卒中リスクを減らせます。」
理由が理解できれば、患者さんは行動の必要性を納得できます。逆に理由がわからないままでは、行動は定着しません。
身近な例や比喩を使う
医療用語や数値だけでは患者さんの頭に入りにくいことがあります。
- 食事制限は「おにぎり1個分の量」など身近な例で説明
- 血糖値のコントロールは「車のブレーキ」に例える
- 薬の効果は「毎日水やりをする植物のよう」と表現する
比喩や具体例は、記憶に残りやすく、日常生活でも思い出しやすい効果があります。
小さなステップで提案する
行動変容は一度に大きな変化を求めないことが成功のカギです。
例:「毎日30分運動してください」ではなく、「週2回、15分歩くことから始めましょう」など、達成しやすい目標を設定します。小さな成功体験を重ねることで、継続へのモチベーションが高まります。
また、ステップの進行は必ず確認し、達成できたら次のステージへ移るようにします。こうすることで、負担感を最小限に抑えつつ着実な改善が可能になります。
患者さんの意見を引き出す
一一方的な指示ではなく、患者さんに参加してもらう姿勢が大切です。
- 「この方法ならできそうですか?」
- 「無理のない範囲でどこから始めたいですか?」
- 「続けるための工夫は何かありますか?」
こうした質問により、患者さん自身が行動計画の主体となります。さらに、患者さんが自分の言葉で決めた内容は、実行されやすく継続率も高くなります。これにより、行動変容は一時的なものではなく習慣へと変わっていきます。
理解度を確認しながら話す
説明だけで終わらせず、理解度を確認しましょう。
ティーチバック法を使って「この薬はどう飲むことになっていましたか?」と聞き返し、正しく説明できれば理解が定着している証拠です。もし誤解があれば、その場で修正できます。
また、この確認は患者さんにとっても「自分はちゃんと理解している」という安心感につながります。結果として、自己管理への自信や責任感を高める効果も期待できます。
ポジティブなフィードバックを忘れない
患患者さんが行動を起こしたら必ず評価します。
- 「よく頑張って続けてくれましたね」
- 「数値が改善していますよ」
- 「以前よりも体調が安定してきました」
成果が小さくても努力を認めることで、次の行動につながります。特に長期的な取り組みでは、途中経過を褒めることが継続の原動力となります。
定期的にポジティブな言葉をかけることで、患者さんとの関係性も強化されます。
継続的なフォローで定着を支援
行動変容は一度の説明で終わるものではありません。
次回診察時に経過を尋ね、うまくいかなかったときは責めずに原因を探り、代替案を一緒に考えます。
例:「忙しくて歩けなかった」→「買い物のときに少し遠回りして歩きましょう」など現実的な案に置き換える。さらに、必要に応じて家族や周囲の協力を得られるよう提案すると、環境面からも行動を支えやすくなります。
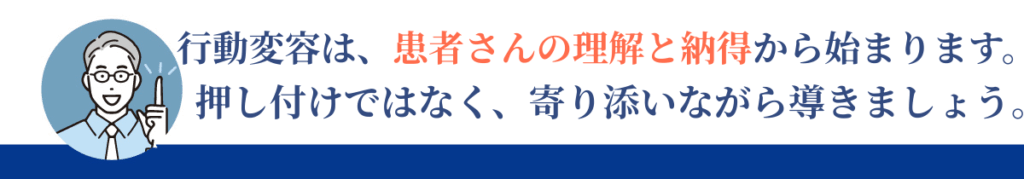
まとめ
患者さんの行動を変えるためには、信頼関係を基盤に、理由の明確化、わかりやすい説明、小さなステップ、主体的参加、理解度の確認、ポジティブな評価、そして継続的なフォローが欠かせません。
これらを一つひとつ丁寧に積み重ねることで、患者さんは自らの意思で行動を選び、習慣として定着させることができます。最終的には、患者さんの健康状態が向上し、医療者との信頼もさらに深まります。
無料リソースのご案内
接遇の質を見直し、今よりさらに良くなれば患者さんとの信頼関係をさらに築くことができます。
当社では接遇研修や満足度調査「E-Pサーベイ」のご相談も承っています。お気軽にご相談ください。
ぜひ下記からご活用ください。
▶ 「接遇・ホスピタリティ」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます