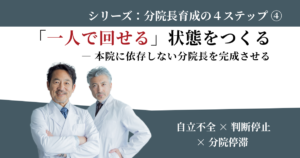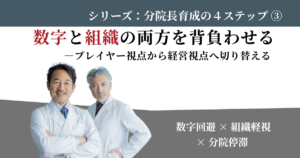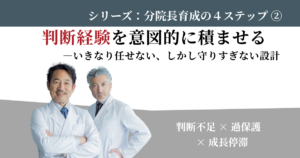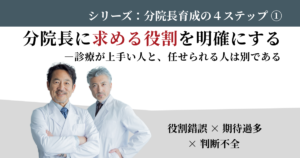院内や職場で交わされるあだ名やため口は、一見すると雰囲気を和ませ、スタッフ同士の距離を縮める要素に見えます。しかし医療や接客の現場では、その文化が必ずしもプラスに働くとは限りません。患者さんからは「馴れ合い」と映り、信頼を損なう可能性もあるのです。
本記事では、院内コミュニケーションにおけるあだ名・ため口のリスクと線引きの考え方、そして敬意を保ちながら職場の温かさを守る方法について解説します。
院内のあだ名・ため口問題 ~職場文化が患者の信頼に与える影響~
1. あだ名・ため口が生まれる背景
職場内でのあだ名やため口は、親しみやすさやフラットな関係づくりの一環として自然に生まれることがあります。特に、同世代の若手スタッフやアルバイトが多い職場では、ごく自然に呼び方が崩れやすいものです。
- 仲間意識を強め、距離を縮める目的で使われる
- 上下関係を和らげ、コミュニケーションを取りやすくする意図がある
- 職場の雰囲気を柔らかくしたい気持ちから広がりやすい
こうした背景には「良かれと思って」という意識もありますが、医療サービスや接客の場では必ずしもプラスに働くとは限りません。患者さんや来訪者の目にどう映るかという視点を欠くと、意外なリスクにつながります。
2. 職場内だけで済まないリスク
あだ名やため口は、スタッフ間では親しさの象徴でも、外から見ればまったく違う印象を与えます。特に医療現場では「信頼感」が何より大切です。
- 患者さんから見て「馴れ合い」「緊張感の欠如」と受け取られる
- 指示があいまいになり、業務効率や安全性に悪影響を及ぼす
- 新人や立場の弱いスタッフが仲間に入りにくくなる
- 院長への敬意が薄れ、組織文化が崩れるきっかけとなる
たとえば、患者さんの前で「○○ちゃん、ちょっと来て」と呼ぶ光景を見たらどうでしょうか。患者さんはそのスタッフを「専門職」として見られず、不安を抱くかもしれません。職場の空気を和ませるはずのあだ名やため口が、逆に「信頼の低下」を招くケースは少なくありません。
3. 線引きをどう考えるか
禁止一辺倒では「ギスギスした職場」になってしまう一方で、野放しでは信頼を失います。そこで必要なのは「TPOに応じた線引き」です。
- 患者さんの前では必ず敬語を使う
- スタッフ同士の呼び方は原則名字+さん付け
- あだ名はスタッフルームなど私的空間に限定
- ため口はプライベートに留め、勤務中は避ける
こうしたルールを「なんとなく」ではなく、明文化して全員で共有することが重要です。単純ですが「患者さんの前=敬語」「勤務中=名字+さん」といったシンプルな基準を徹底するだけで、職場の印象は大きく変わります。
4. スタッフ間の関係づくり
あだ名やため口を完全に排除しなくても、スタッフ同士の関係を良好に保つ方法は十分にあります。たとえば「ありがとう」「助かります」「お疲れさまです」といった肯定的な声かけは、敬語でも親しみやすさを損なわず、むしろお互いの信頼を深めます。
逆に、表面上は仲良さそうでも、雑な呼び方やため口ばかりの関係は、長期的に見ると誤解や摩擦の原因になりやすいのです。「敬語=堅苦しい」とは限らず、むしろ敬語の中に優しさや感謝を込めることで、安心感や一体感を高められます。
つまり大切なのは「馴れ合いではなく、敬意を持った親しさ」を文化として育てることです。職場の温かさは、呼び方や口調ではなく、日々の小さな配慮や感謝の積み重ねによって形づくられるのです。
5. 院長が果たすべき役割
あだ名やため口問題は、最終的に院長やリーダーの姿勢で決まります。方針を明確に示さずに曖昧にしてしまうと、スタッフごとに解釈がバラバラになり、混乱や不公平感が生まれます。
- 朝礼や会議で「患者さんの前では敬語を徹底」と繰り返し伝える
- 新人研修の段階で「呼称ルール」を共有し、最初から習慣化する
- スタッフルーム内での呼び方はある程度自由にし、緊張を和らげる
- 院長自身が「名字+さん付け」で呼び、模範を示す
特に院長やリーダー自身の言動は強い影響力を持ちます。院長やリーダーが率先して敬語や適切な呼称を使えば、スタッフも自然と同じ行動をとります。ルールは紙に書くだけでは機能しません。日々の行動で示し、文化として根づかせることが大切です。
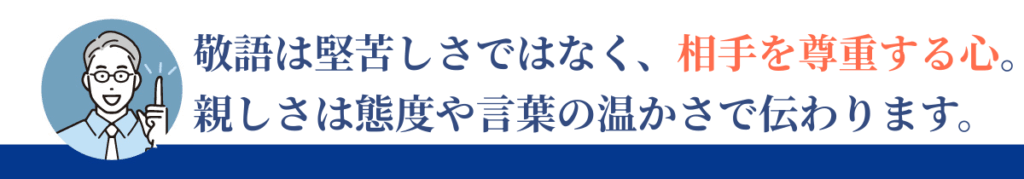
まとめ
あだ名やため口は、職場の雰囲気を和ませる要素として使われる一方で、患者さんや外部の目には「信頼を損なう要因」として映るリスクがあります。大切なのは「禁止か容認か」の二択ではなく、「どこでどう使うか」という線引きを明確にし、組織として共有することです。
スタッフ間の信頼を保ちながら、患者さんからの信頼も守る。その両立を可能にするのが、敬語を基本に据えた職場文化です。敬語は堅苦しさではなく、相手を大切にする気持ちの表現です。親しさは「雑さ」ではなく「思いやり」で示すべきなのです。
院長が方針を明確に打ち出し、自ら模範となることで、医院や職場全体に「敬意ある文化」が育ちます。その文化こそが、患者さんの安心感とスタッフの働きやすさを両立させ、組織力を高める基盤となるのです。
【無料】75%公開版チェックリストをご提供中
本記事では、院内でのあだ名やため口が職場文化や患者の信頼に与える影響について解説しました。
こうしたコミュニケーションの課題を改善し、より良い職場文化を築くには、医院や組織全体の現状を体系的に把握することが欠かせません。
そこで、経営の現状と改善ポイントを客観的に整理できる「BSC(バランス・スコアカード)チェックリスト 75%公開版」を無料でご提供しています。
- 組織の強み・弱みを数値で確認できる
- 院長や経営者の頭の中にある課題を「見える化」できる
- 評価制度や人事制度の導入準備として活用できる
下記ボタンよりぜひご請求いただき、信頼される職場文化づくりと経営改善の第一歩としてご活用ください。
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます