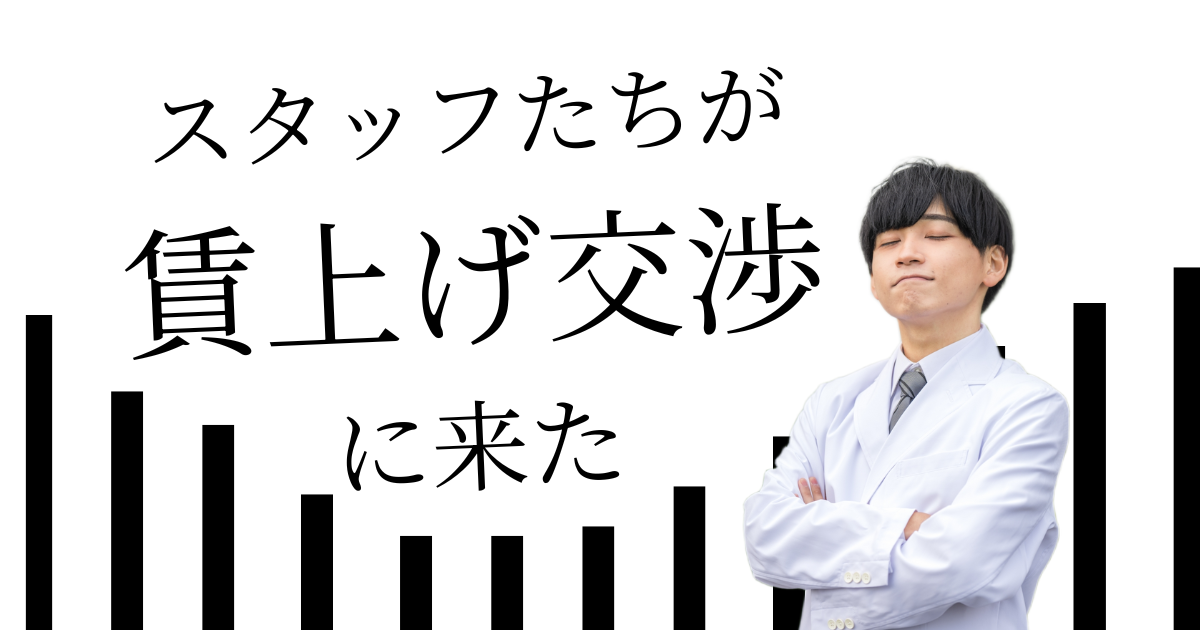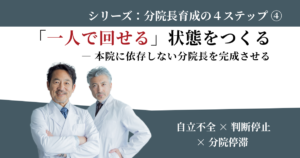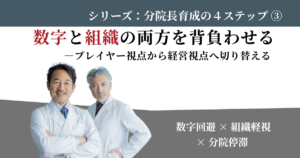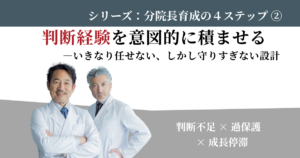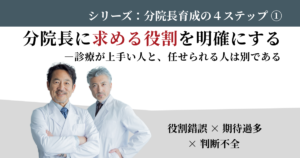スタッフの給与に関する話題は、組織運営においてとてもデリケートな領域です。
特に注意が必要なのは、個人として要望を伝えるのではなく、複数のスタッフを巻き込んで「一斉に声を上げる」という形で交渉してくるケースです。こうした場面は、クリニックの空気を一変させ、院長に大きな心理的負担を与えかねません。しかし、感情的に対応してしまうと火に油を注ぐ結果となります。
ここでは、冷静かつ組織的に対処するための視点を整理します。
他人を巻き込んで賃上げ交渉をしてくるスタッフに対して
個別要望と集団交渉の違いを理解する
まず区別すべきは「個人の要望」と「複数人による交渉」です。
- 個別要望:正当に耳を傾け、制度や評価基準に基づいて検討すべき
- 集団交渉:背後に「不満の連鎖」や「組織的圧力」があるケースが多い
集団での交渉は、実際の金額よりも「院長がどう対応するか」がスタッフ全体の信頼に直結します。そのため、感情ではなく「ルール」に基づいた対応が不可欠です。
就業規則と評価制度に立ち返る
このような場面では、まず「就業規則」や「評価制度」に基づいて話を進めることが重要です。
- 「給与の見直しは年1回の評価面談に基づいて行う」
- 「昇給は勤務態度・業務遂行度・役割の拡大を基準に決定する」
といった取り決めを示すことで、院長の判断が恣意的ではないことを明確にできます。前回の記事で触れたように、就業規則はクリニックの憲法です。交渉の場面でも、それを「拠り所」として活用することで、冷静なやりとりが可能になります。
感情的な議論を避ける工夫
スタッフが複数人で来たときに最も避けたいのは、感情論に流されてしまうことです。そのためには以下の工夫が有効です。
- 一度に答えず「持ち帰って検討します」と時間を置く
- 話し合いは必ず記録を残し、事実に基づいて整理する
- 交渉の場は可能であれば院長一人ではなく、事務長や顧問社労士も同席させる
これにより、院長個人の感情に左右されない「組織としての対応」を示すことができます。
スタッフの声の裏側を探る
複数人で賃上げ交渉に臨む背景には、必ず「給与そのもの」以外の要因が潜んでいます。例えば:
- 仕事量や役割に不公平感がある
- 評価の仕組みが見えにくく、納得感がない
- 頑張りを認めてもらえていないと感じている
このような不満を「賃金」という形で表現していることが少なくありません。したがって、金額の話に入る前に「なぜこの要求が出てきたのか」を分析する姿勢が大切です。
建設的な着地点をつくる
実際に交渉があった場合、すぐに昇給を約束する必要はありません。むしろ、拙速な回答は後々の基準を揺るがします。建設的に着地させるためには:
- 「給与をどう上げるか」ではなく「給与を上げるために何が必要か」を共有する
- 評価項目や成果の指標を再確認し、達成したときに昇給できる仕組みを説明する
- 必要に応じて「評価制度の見直しプロジェクト」などを立ち上げる
こうすることで、スタッフに「交渉したから上がった」のではなく「制度と努力で上がった」と理解してもらえるようになります。
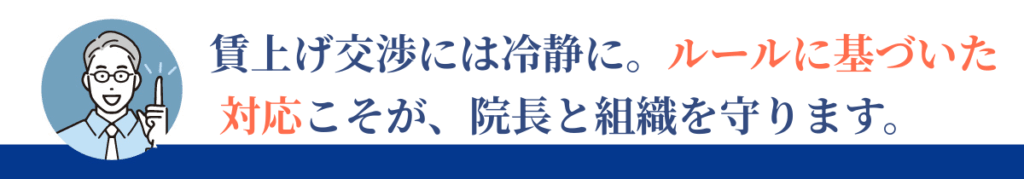
まとめ
他人を巻き込んで賃上げ交渉をしてくるスタッフへの対応は、院長にとって試される瞬間です。
感情的に否定したり、安易に応じたりするのではなく、就業規則や評価制度を基盤にした「組織としての答え」を示すことが重要です。また、表面的な要求の裏には「不公平感」や「承認欲求」が潜んでいることが多いため、根本的な改善につなげる姿勢も忘れてはなりません。
最終的には「給与の議論」ではなく「組織の信頼づくり」の一環と捉えることが、院長に求められるリーダーシップなのです。
無料リソースのご案内
組織力を強化し、医院の成長を加速させたいとお考えの院長へ。
経営の現状と改善ポイントを客観的に把握できる「BSCチェックリスト(75%公開版)」を無料でご提供しています。
ぜひ下記ボタンより請求し、自院の組織づくりにお役立てください。
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます