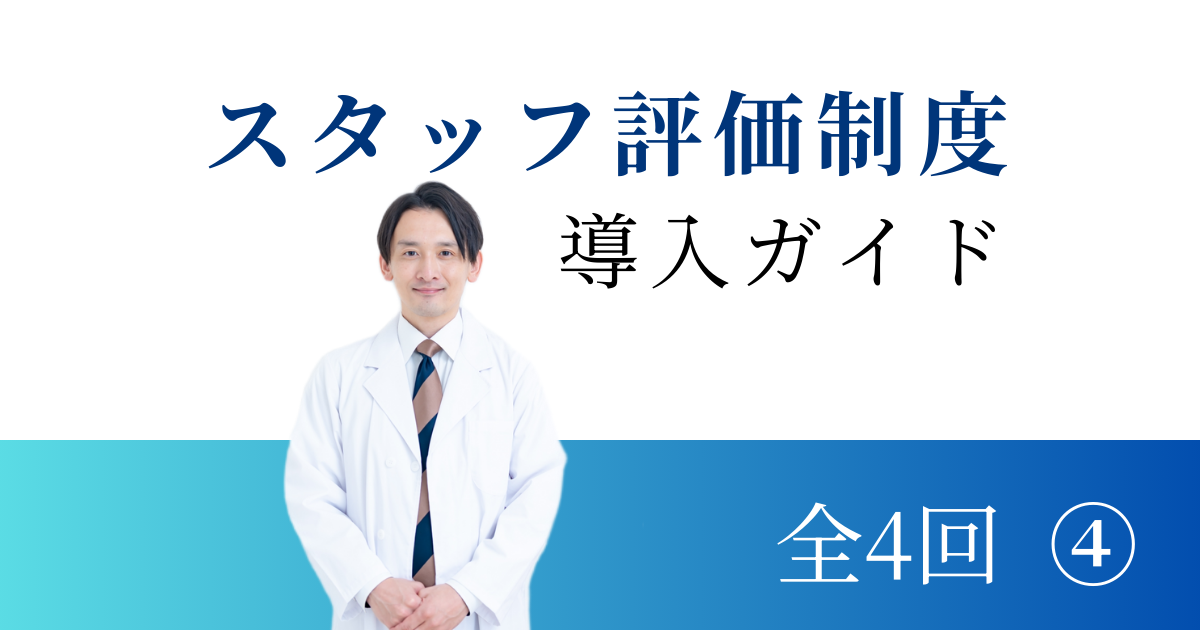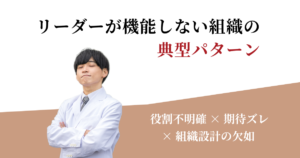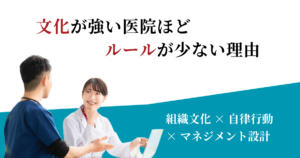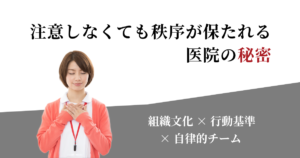評価制度は「作ること」よりも「どう活かすか」で成果が決まります。どれほど丁寧にシートを整えても、評価を伝える面談が形だけになってしまえば、スタッフにとっては負担や不信感につながりかねません。
逆に、評価結果を適切にフィードバックし、給与やボーナスへ透明性を持って反映できれば、スタッフは「努力が報われる」と感じ、モチベーションと定着率の向上につながります。
本記事では、評価結果をどのように運用すればよいかを整理し、フィードバック面談の進め方、トラブルを防ぐ仕組み、給与・ボーナスへの反映方法など、実際に医院で役立つ工夫をご紹介します。
評価結果の活かし方と運用のコツ
1. 評価結果をどう伝えるか
評価の内容は、伝え方によって受け取る印象が大きく変わります。数字や点数だけを示すと「査定をされた」という印象を持たれがちですが、良い点と改善点を具体的に伝えれば、前向きな学びになります。院長自身が伝える姿勢を意識することが、制度の定着に直結します。
- 面談では必ず「良かった点」から話す
- 改善点は具体的に「どの行動を変えればよいか」を伝える
- 数字は結果の裏付けとして補足的に活用する
- 一方的な通告ではなく、双方向の対話にする
評価結果は「人を裁くもの」ではなく「成長のためのメッセージ」であることを意識することが重要です。
2. フィードバック面談の進め方
評価面談は、スタッフのモチベーションを高める貴重な機会です。短時間で済ませるのではなく、準備をして臨むことで成果が大きく変わります。評価者にとっても、スタッフの考えや課題感を知る大切な場となります。
- 事前に評価シートを共有し、自己評価も記入してもらう
- 面談時間を十分に確保し、落ち着いた環境で行う
- 「できたこと」「次に取り組むこと」をバランスよく扱う
- ゴール設定を一緒に行い、次の評価までの道筋を共有する
スタッフが「自分の成長に寄り添ってくれている」と感じれば、評価制度が信頼され、院内全体の雰囲気が良くなります。
3. トラブルを防ぐ仕組み
評価は人間関係に関わるため、誤解や不満につながるリスクもあります。制度を長期的に運用するためには、透明性と再現性を確保する仕組みが欠かせません。
- 評価基準を明文化し、事前に全員と共有しておく
- 複数の評価者(院長+主任など)によるチェック体制を整える
- 評価理由をシートに残し、後で見返せるようにする
- 面談記録を保存し、改善のプロセスを追えるようにする
仕組みでトラブルを予防することで、院長もスタッフも安心して評価制度に取り組めます。これは制度を「続ける力」につながります。
4. 給与・ボーナスとの連動
評価を給与やボーナスに結びつけると、制度は形骸化せずに生きたものになります。ただし、最初から大きな差をつける必要はありません。小さな加点方式から始め、スタッフが「努力すれば報われる」と実感できる範囲で運用することが大切です。
昇給基準や賞与加算のルールを透明化することで、納得感が高まり、モチベーション維持につながります。
5. 院長が意識すべき運用のコツ
評価制度は「作ったら終わり」ではなく、日々の運用で生きてきます。院長が制度をどのように扱うかで、スタッフの信頼度が変わります。制度を「人を責める道具」にせず「成長を支援する仕組み」として使うことが重要です。
- 定期的に制度を見直し、現場に合った形に更新する
- 面談は「指摘」ではなく「伴走」の場と位置づける
- 評価を通じて医院全体の課題や改善点を発見する
- 成果が出たスタッフは積極的に称賛し、院内に共有する
院長が「評価は成長支援」という姿勢を示せば、スタッフも前向きに受け止め、医院全体の組織力が高まっていきます。
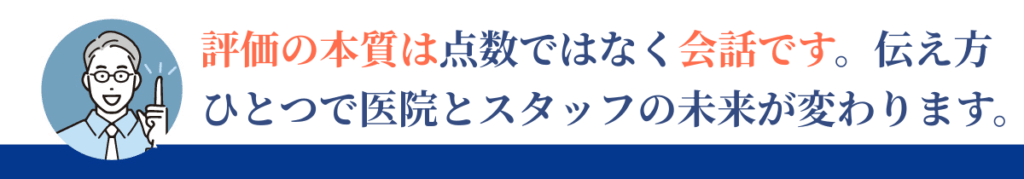
まとめ
評価制度は、導入よりも「活かし方」にこそ価値があります。丁寧なフィードバック面談と透明な仕組み、適度な給与連動を組み合わせることで、制度は単なる査定ではなく成長を支える土台に変わります。
院長自身の姿勢が信頼をつくり、スタッフのモチベーションを引き出し、医院全体の成長を後押ししていくのです。
▶医院経営者のためのスタッフ評価制度ガイドシリーズ:まとめページに戻る
無料リソースのご案内
スタッフ評価制度を導入するには、医院全体の方向性や課題を整理しておくことが大切です。
そこで、経営の現状と改善ポイントを客観的に把握できる「BSCチェックリスト(75%公開版)」を無料でご提供しています。
- 組織の強み・弱みを数値で確認できる
- 院長の頭の中にある課題を「見える化」できる
- 評価制度や人事制度の導入準備として活用できる
下記ボタンより請求いただき、自院の組織づくりにぜひお役立てください。
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます