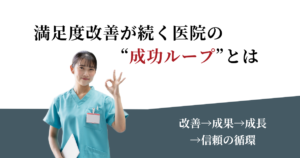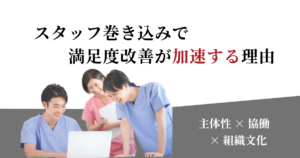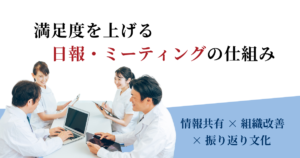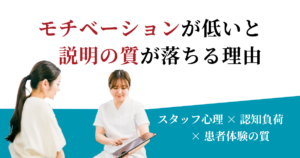患者さんの満足度を把握するため、アンケート調査を行う医院は増えています。
特に開業記念やキャンペーンのタイミングで単発調査を実施するケースは多く、その場で得られた結果をもとに改善策を立てることもあります。しかし、単発のアンケートだけでは見えない情報や変化が数多く存在します。
今回は、単発調査の限界と、継続的な測定がもたらす本質的な改善効果について考えます。
患者満足度の落とし穴|単発アンケートだけでは見えない変化
単発調査の限界
単発アンケートは、現状の瞬間的なスナップショットを切り取るに過ぎません。そのため、改善施策の効果や季節要因、スタッフ体制の変化など、時間の経過とともに変わる要素を把握できないという課題があります。
例えば、4月に実施したアンケートで「待ち時間が長い」という声が多かった場合、すぐに予約システムや診療フローを見直すかもしれません。しかし、その改善が本当に患者さんの満足度向上につながったかは、半年後や1年後に再測定しなければ分かりません。
また、単発調査には次のようなリスクがあります。
- 季節やイベントによる一時的な満足度の変動を、恒常的な課題と誤解してしまう
- 院内の一部スタッフや特定日の出来事が結果に大きく影響する
- 調査結果が改善の方向性よりも一時的な感情に左右されやすい
継続測定の重要性
満足度調査は、改善の「前後比較」と「変化の傾向」を追うことが重要です。単発の結果では「今どうか」しか分かりませんが、継続測定を行えば「改善が持続しているか」「新たな課題が出てきていないか」を確認できます。
継続測定がもたらす利点は以下の通りです。
- 改善策の効果検証が可能になり、投資対効果を明確にできる
- 季節変動や一時的要因を切り分けて評価できる
- 小さな変化を早期に発見し、深刻化する前に手を打てる
- データをもとに院内の方向性を共有しやすくなる
データ活用で「勘」から脱却
多くの医院では、患者さんの声を大切にする一方で、その解釈や対応が感覚的になりがちです。単発アンケートでは特に、院長やリーダーが強く印象に残った意見に引きずられて判断してしまうことがあります。これでは、スタッフ間での温度差や方向性のズレが生じる可能性があります。
継続的なデータがあれば、院内会議で数値を共有し、改善策の成果や課題を客観的に話し合えます。これは、感情ではなく事実に基づいたマネジメントを可能にします。
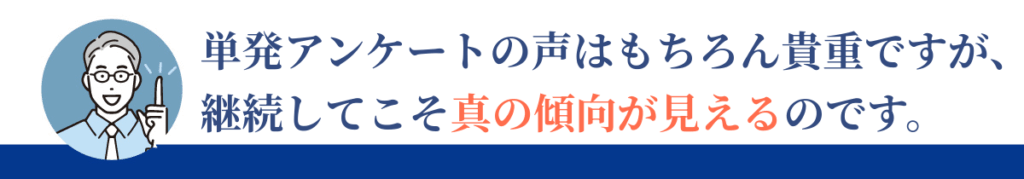
まとめ
患者さんの声は医院運営に欠かせない重要な情報であり、その評価や意見は日々の診療方針やサービス改善の方向性を左右します。しかし、その判断を一度きりの調査に頼ってしまうと、偶然の要因や一時的な状況に影響され、誤った結論に至る可能性があります。
継続的な測定を行うことで、改善策の効果を確実に検証できるだけでなく、小さな変化や兆しを早期に発見し、タイムリーに対応することが可能になります。こうした取り組みは、患者さんとの信頼関係を深め、医院全体の成長を長期的に支える大きな土台となります。
つまり、感覚や印象に頼らず、データと事実をもとに判断する姿勢が、安定した経営と質の高い医療提供への近道となるのです。
E-Pサーベイ継続運用のメリット
E-Pサーベイは、患者さんの満足度を継続的かつ手軽に測定できるツールです。単発調査とは異なり、期間を設定して複数回の調査を行うことで、傾向や改善効果を可視化します。
さらに、質問内容を柔軟に変更できるため、
- 新しいサービスや設備導入の効果測定
- 季節ごとの特定課題(例:花粉症シーズンの混雑状況)
- スタッフ配置やシフト変更後の影響確認
といった多様なテーマにも対応可能です。
E-Pサーベイは今、半年間無料で満足度調査をスタートできます。
下記からエントリー可能です。
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます