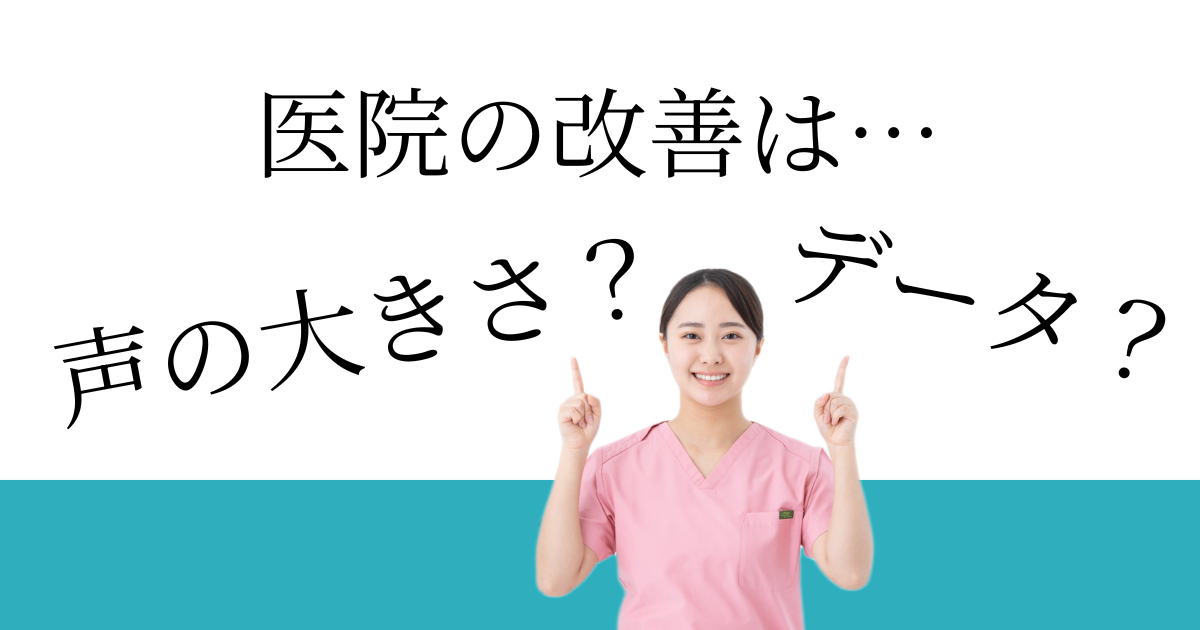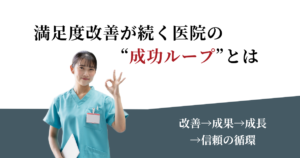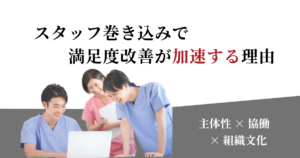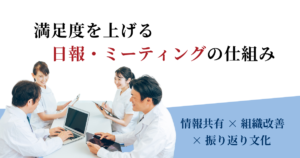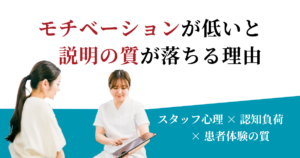患者さんの満足度を高めるためには、感覚や一部の声だけで判断するのではなく、全体の傾向をデータで把握することが欠かせません。とくに、クレームや要望の大きさに引っ張られすぎると、重要な改善点を見誤ることがあります。
本稿では、患者アンケート結果を「声量」ではなく「データ」で判断する重要性と、その実践方法についてお伝えします。
改善点は「声の大きさ」ではなく「データ」で決める
声の大きさではなく、データで判断する意味
医院に寄せられる声には、日常的な感想から強いクレームまで、さまざまなトーンがあります。
特に強い口調の要望やクレームは目立ちやすく、改善の優先順位を高く設定しがちです。
しかし、それが必ずしも多くの患者さんに共通する課題とは限りません。
データで判断するメリットは以下の通りです。
- 感情や印象に左右されない
- 少数意見と多数意見を切り分けられる
- 満足度に直結する要素を特定できる
こうした分析を行うことで、限られた時間や予算を本当に効果のある改善に集中できます。
満足度との関連性を把握する
アンケート結果の中には、患者さんの満足度に強く影響している要素と、あまり影響していない要素があります。例えば、待ち時間や説明のわかりやすさは満足度に直結しやすい一方、雑誌の種類や駐車場の広さは影響度が低い場合もあります。
この違いを把握するには、次の流れが有効です。
- アンケート項目ごとの満足度平均を算出する
- 全体満足度との相関を計算する
- 相関の高い項目を改善優先度の上位に置く
こうした分析を継続することで、医院の成長に直結する改善ポイントが見えてきます。
感情に流されないための工夫
データを活用する一方で、現場の感情や直感も無視はできません。そこで有効なのは「事実」と「感情」を分けて整理することです。
- 事実:アンケート結果や数値データ
- 感情:現場スタッフや患者さんの生の声
このように分けて考えると、感情は尊重しつつも、最終判断はデータで行えるようになります。
まとめ
患者さんの声は医院運営に欠かせない情報ですが、判断基準を「声の大きさ」ではなく「データ」に置くことで、的確な改善が可能になります。データと感情を切り分け、満足度との関連性を見極めることが、長期的な信頼と成果につながります。
さらに、数値化された結果はスタッフ全員が共有しやすく、課題の優先順位づけや改善策の明確化にも役立ちます。感覚だけに頼らない運営は、医院全体の方向性を安定させ、持続的な成長を後押しします。
E-Pサーベイで両方の測定を実現
患者アンケートをより効果的に活用するには、集計だけでなく相関分析や傾向把握が欠かせません。
弊社の【E-Pサーベイ】なら、その仕組みを手間なく導入できます。従業員満足度調査もeNPS®調査も、同じフォームで設定・実施できます。
- 設問は自由に設定可能
- eNPSの自動集計機能付き
- 回答結果から総合満足度や推奨度との相関を自動分析
- 初期導入支援付きで、すぐに運用開始できる
感覚や一部の声に左右されず、データに基づいた改善を進められます。
E-Pサーベイなら、半年間無料で満足度調査をスタートできます。
下記からエントリー可能です。
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます