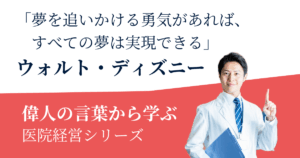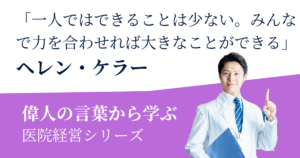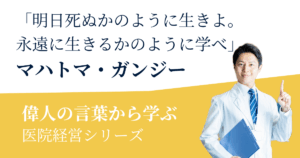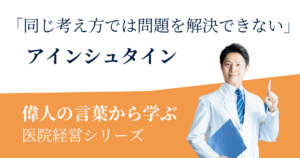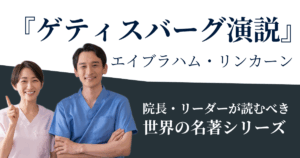医院経営において、売上や来院数などの数字をスタッフにどこまで共有するかは、多くの院長が一度は悩むテーマです。
公表すれば組織の透明性やモチベーション向上につながる一方、数字が一人歩きして誤解や不満を生むリスクもあります。
今回は、数字を公表する際のメリット・デメリット、公表範囲の考え方、そして運用のヒントをご紹介します。
医院の数字、どこまで公表する?
なぜ数字の公表が議論になるのか
数字は経営の現状を示す「事実」です。
事実を共有することで、スタッフは医院の状況を理解し、自分の行動を改善する材料を得られます。
しかし、同じ数字でも「院長の視点」と「スタッフの視点」では受け止め方が異なります。
売上が上がっていると聞けば「経営は安定している」と感じる人もいれば、「ならば給与も上げてほしい」と考える人もいます。
この“受け止めの差”が、数字の公表に慎重になる理由です。
公表するメリット
- 組織の一体感が高まる
売上や来院数、KPI(重要業績評価指標)を共有することで、スタッフは「医院全体の目標」に意識を向けやすくなります。
数字が伸びたときはチームで成果を喜び合え、達成感を共有できます。 - 業績向上への主体性が生まれる
数字は結果であり、結果の裏には行動があります。
スタッフが数字を意識すると、自分の業務と医院全体の成果を結びつけて考えるようになります。 - 課題の早期発見につながる
来院数や定着率などの変化を全員で把握していれば、業務フローの改善点や患者さん対応の課題が早めに浮かび上がります。
公表するデメリット・リスク
- 誤解や不満を招く可能性
経営の数字は単純な増減だけで判断できません。
例えば売上が伸びても、設備投資や人件費増加で利益は減っていることもあります。
こうした背景を理解しないまま数字だけを見て、誤解や要求が増える場合があります。 - 数字だけにとらわれる
数字は重要ですが、患者さん満足度やスタッフの働きやすさといった“数値化しにくい価値”がおろそかになる危険があります。 - 情報流出のリスク
意図せず外部に数字が漏れ、競合に参考にされる可能性もあります。
特に売上や利益などの経営指標は慎重な扱いが必要です。
公表する数字の範囲と頻度
数字を公表する際は「範囲」と「頻度」を事前に決めておくことが重要です。
- 範囲の例
- 来院数(新患・再来)
- 治療ごとの件数
- 定着率・キャンセル率
- 保険・自費の割合
- KPI(例:カウンセリング成約率、リコール率)
※売上や利益は慎重に扱い、全額ではなく前年比や達成率など加工して伝える方法もあります。
- 頻度の例
- 月次:来院数、定着率、KPI
- 四半期:売上達成率、前年比
- 年次:年間総括と来期目標
公表の方法と運用のヒント
- 数字だけでなく背景を説明する
数字はあくまで結果です。必ず背景や理由、今後の改善方針とセットで伝えます。 - 成果はチームで喜び、課題は建設的に議論
数字が良かった時はスタッフの努力を称賛し、悪かった時は責任追及ではなく改善策を話し合う姿勢が大切です。 - 見える化ツールを活用
グラフや表を使えば変化が直感的に理解しやすくなります。
スタッフルームに掲示する、月例ミーティングで共有するなど方法を固定化すると習慣になります。
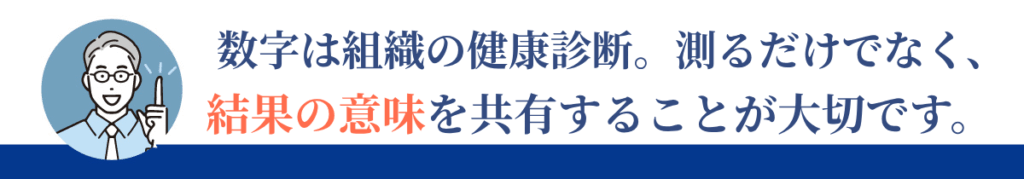
まとめ
数字の公表は、組織文化や院長の経営方針によって最適解が変わります。
重要なのは、「何のために共有するのか」を明確にし、その目的に合った範囲・方法・頻度で運用することです。
数字はチームを成長させる強力なツールですが、使い方を誤れば逆効果になります。
背景説明と目的意識を持ち、数字を“全員で成長するための指標”として活用しましょう。
【無料】75%公開版チェックリストをご提供中
今回の連載と連動し、BSC導入のための「75%公開版チェックリスト」を無料でご提供しています。
スタッフとの話し合いや、導入検討のたたき台としてご活用いただけます。
ご希望の方は、下記より資料請求または無料相談にお進みください。
▶ 「経営戦略」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます