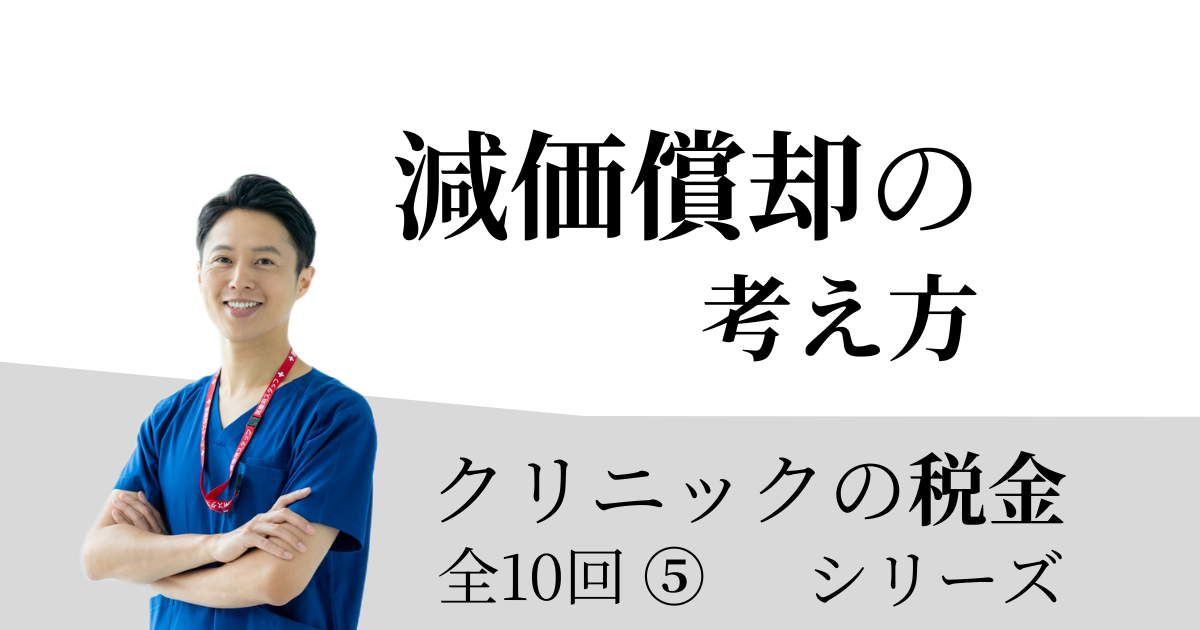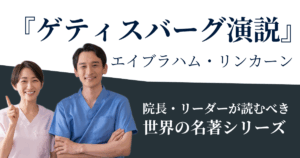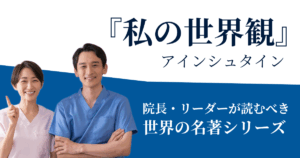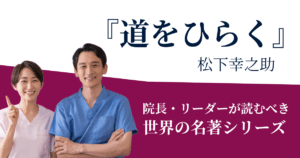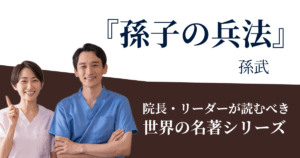クリニックを経営するうえで避けて通れないのが「設備投資」です。診療用ユニットやレントゲン装置、CTスキャナ、電子カルテシステムなど、高額な医療機器を導入する場面は数多くあります。さらに内装工事や建物の改修なども含めると、開業時だけでなく、継続的に数百万円から数千万円単位の投資が必要です。
こうした資産は購入した年度に一括で経費化できるわけではありません。「減価償却」という仕組みに従い、資産の耐用年数に応じて少しずつ費用化していきます。もしこの仕組みを理解せずに資金計画を立てると、「現金は出ていったのに経費に落ちない」という状況に直面し、黒字倒産のような資金繰りリスクを抱えることになりかねません。
減価償却は単なる会計処理ではなく、経営判断や資金繰りに直結する重要な考え方です。本稿では、減価償却の基本からリースとの比較、経営上の活用ポイントまで整理して解説します。
クリニックの税金 ⑤|減価償却の考え方
1. 税減価償却の基本的な仕組み
減価償却とは、固定資産を耐用年数にわたって少しずつ経費化していく会計処理を指します。たとえば、1,000万円のCTを購入した場合、その年に全額を経費とすることはできません。税法で定められた耐用年数(医療機器は通常5〜10年)に応じて、毎年決まった額を費用に計上していきます。
つまり、現金支出は初年度に発生するが、損金算入は複数年に分割されるというズレが生じます。このズレを理解していないと、資金繰りが厳しいのに帳簿上は黒字という状況が起こり得ます。
減価償却は「資産の価値を時間の経過とともに費用に振り分ける仕組み」であり、実際にお金が出ていくわけではありません。そのため、資金繰り管理のうえでは「帳簿上の費用」と「現金の流れ」を分けて考える必要があります。
耐用年数と資金繰りの関係
医療機器や内装は、それぞれ税法で耐用年数が定められています。例えば、歯科用ユニットは耐用年数8年、X線装置は6年、建物付属設備は15年といった具合です。耐用年数が長いほど、毎年の減価償却費は小さくなりますが、その分だけ資金回収までの見通しも長くなります。
ここで大切なのは、減価償却費の計上と実際のキャッシュアウトのタイミングを一致させないことです。初年度に大きな資金支出が発生しているのに、経費化は少しずつしかできない。この「帳簿と現金のギャップ」を常に意識して、資金計画を立てなければなりません。
例えば、5,000万円の設備投資を借入金で賄った場合、毎月の返済額は資金繰りに直接影響します。一方で、帳簿上は減価償却費として数百万円ずつしか費用になりません。「黒字なのにお金が足りない」 という状況を避けるには、耐用年数を前提とした返済スケジュールとキャッシュフロー計画を必ずセットで考える必要があります。
リースと購入の比較
高額な医療機器を導入する際、多くの院長が悩むのが「購入」か「リース」かの選択です。
- 購入の特徴
- 初期投資が大きい
- 所有権が残るため、売却や担保利用が可能
- 減価償却により複数年にわたり費用化
- リースの特徴
- 初期投資が不要、月々の支払いで導入可能
- 契約終了後は所有権が残らない
- リース料はそのまま経費化できる
- 総額では購入より割高になるケースが多い
リースは資金繰りを平準化できる点が大きなメリットです。毎月一定額を経費計上できるため、キャッシュフロー管理がしやすくなります。ただし長期的に見ると支払総額が購入よりも多くなる傾向があり、更新のたびに再契約が必要です。
どちらを選ぶべきかは、資金余力、設備更新の頻度、節税効果 の3つを総合的に判断して決めることが望ましいでしょう。
減価償却の経営的インパクト
減価償却は「節税テクニック」と誤解されがちですが、実際には経営戦略の一部です。大きな設備投資を行えば、毎年の減価償却費は利益を圧縮し、法人税の負担を軽減します。これは短期的には節税効果となりますが、同時に「利益が少なく見える」ことで金融機関からの評価に影響を与える可能性もあります。
銀行融資の審査では、利益水準だけでなく、減価償却費を加えた「キャッシュフロー」を重視します。そのため、減価償却の仕組みを理解し、利益と現金収支を分けて説明できることは、金融機関との関係構築においても有利に働きます。
また、将来的な更新投資に備えるためには「減価償却費相当額を内部留保する」という考え方も重要です。帳簿上の費用である減価償却費を実際の資金として確保しておくことで、次の設備投資をスムーズに行うことができます。
実務上の注意点
減価償却をめぐっては、税務調査で指摘を受けやすいポイントもあります。
- 耐用年数を誤って短く設定している
- 資産計上すべきものを経費処理している
- リース契約を誤って資産計上していない
これらのミスは追徴課税や加算税につながる恐れがあります。特に「30万円未満の少額資産は一括経費化可能」という特例を乱用していると、調査時に否認されるリスクが高まります。
専門家と相談し、資産計上と経費処理の線引きを明確にしておくことが、リスク回避の第一歩です。

まとめ
減価償却は単なる会計処理ではなく、資金繰りと経営戦略に直結する重要な仕組みです。高額な設備投資は、現金支出と損益計上のタイミングにズレを生じさせ、黒字でも資金が不足するリスクを生みます。そのため、耐用年数を踏まえた返済計画や資金繰りシミュレーションを必ず行うことが欠かせません。
また、購入とリースの比較検討も大きな経営判断です。資金余力や更新頻度、税務上のメリットを考慮し、自院にとって最適な方法を選ぶ必要があります。減価償却費を内部留保として蓄えておけば、次の設備投資にも備えられ、経営の安定性が高まります。
「減価償却を理解している医院」と「理解していない医院」とでは、将来的な資金繰りの安定性に大きな差が生まれます。単なる数字合わせではなく、経営に活かす知識として捉えることこそが、持続的な医院運営につながるのです。
※税金の取扱いは法改正や解釈変更が随時行われます。必ず顧問税理士にご確認ください。
【無料】75%公開版チェックリストをご提供中
本シリーズでは、クリニック経営に欠かせない考え方や仕組みを整理して解説しています。
その次の一歩として、経営全体を体系的に把握できる「BSC(バランス・スコアカード)75%公開版チェックリスト」を無料でご提供しています。
数値だけに偏らない経営課題の整理や、スタッフと共有できる指標づくりの土台としてぜひご活用ください。
ご希望の方は、下記より資料請求または無料相談にお進みください。
▶BSC(バランススコアカード)については、こちらのまとめからご覧ください。
▶ 「経営戦略」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます