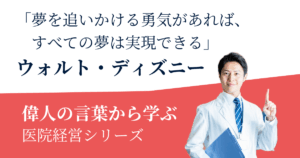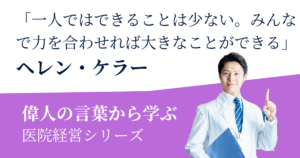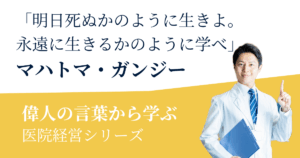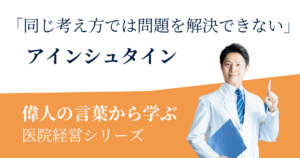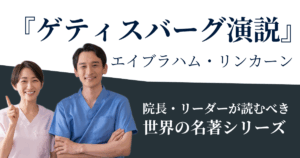スティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』が“自分を磨く”ための書であるとすれば、D・カーネギーの『人を動かす』は“他者を動かす”ための書です。
1936年の初版から世界で1,500万部以上を超えるロングセラーであり、今もあらゆるリーダーシップ論の原点とされています。
医院という小さな組織であっても、院長・リーダーが人を動かす力を持つことは不可欠です。
しかし、力や地位で動かすのではなく、「人が動きたくなる関わり方」を学ぶことが本質。
本稿では、カーネギーの原則を医院マネジメントに置き換えて解説します。
D・カーネギー『人を動かす』― 人の心を動かす「共感と承認」のリーダーシップ ―
1. 批判よりも、理解を
カーネギーは冒頭でこう述べています。
「人を非難する代わりに、理解するように努めよ。」
人は批判されると反発し、理解されると心を開きます。
医院でも、スタッフがミスをしたときに叱責するより、
「なぜそうしたのか?」を聞き、背景を理解しようとする姿勢が大切です。
たとえば、遅刻や確認漏れの裏には、
「不安」「自信のなさ」「体調不良」「家庭の事情」など、表に出ない事情があるかもしれません。
その根を理解することで、“人を責めずに成長を促す対話”が可能になります。
2. 正直で誠実な承認を
カーネギーが最も重視した原則のひとつが、
「心からの賞賛を与えよ。」
人は「認められたい」という欲求に突き動かされて生きています。
これは給与よりも強いモチベーションの源です。
医院においても、
- 小さな改善を見逃さずに伝える
- 「ありがとう」「助かったよ」と即時に言葉にする
- 「あの対応は良かった」と具体的に評価する
といったフィードバックが、スタッフの行動意欲を劇的に高めます。
カーネギーは“お世辞ではなく、誠実な承認”を説きます。
それはおだてることではなく、「相手の努力や姿勢を正しく見る力」です。
3. 人を動かす秘訣は“自発性”を引き出すこと
「人を動かす最良の方法は、相手の中に“その気”を起こさせることだ。」
命令ではなく、相手自身が「やりたい」と思うように導く。
これが院長・リーダーに求められる本当のマネジメントです。
たとえば、
- 「こうしてもらえると患者さんがもっと安心するね」
- 「あなたの工夫があったからうまく回ったよ」
- 「どうしたらもっと良くなると思う?」
といった問いかけは、“考えさせるリーダーシップ”の典型です。
人は「自分で決めた」と感じたときに、最も意欲的に行動します。
院長の仕事は、命令することではなく“動きたくなる環境を整えること”なのです。
4. 医院経営におけるカーネギーの原則
カーネギーの教えは、現代の医院マネジメントにも直結します。
以下の3原則は、特に院長・リーダーに欠かせない視点です。
- 非難より理解を: 問題の根を掘り下げ、信頼関係を壊さない。
- 承認を惜しまない: スタッフの努力を具体的に見て伝える。
- 相手の視点に立つ: どうすれば相手が動きたくなるかを常に考える。
これらは単なるコミュニケーション技術ではなく、「人間理解に基づく経営姿勢」そのものです。
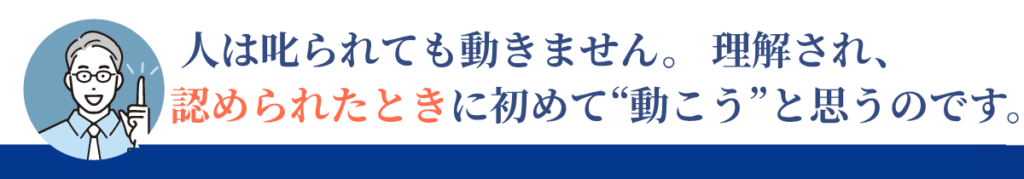
まとめ
カーネギーの『人を動かす』は、人間関係の本質を突いた timeless classic(時代を超える名著)です。
スタッフ教育や組織づくりの現場で悩む院長にとって、
「人を責めず、人を動かす」ためのヒントが詰まっています。
人を変えようとする前に、まず自分の関わり方を変える。
それが、組織を変える第一歩です。
次回は『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健)を取り上げ、
“承認”から一歩進んだ「自立と対等のリーダーシップ」について考えます。
無料リソースのご案内
医院のリーダーシップやスタッフ育成を支える仕組みとして、
「接遇5原則チェックシート」と「BSCチェックリスト(75%公開版)」を無料提供しています。
理念の実践を“測定・改善”の仕組みに変える第一歩として、ぜひご活用ください。
下記から請求をお願いします。
▶BSC(バランススコアカード)については、こちらのまとめからご覧ください。
▶ 「経営戦略」カテゴリの関連記事を探す
▶ カテゴリ検索・人気記事などコラムのトップへ戻る
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます