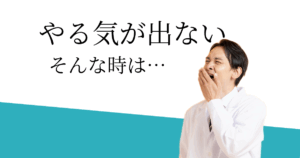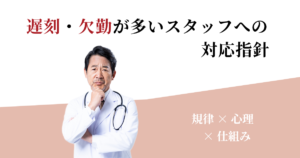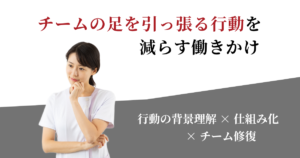休みがちなスタッフにどう接していくべきか? 院長・リーダーの対応指針
「また今日も休みか…」と感じたら
クリニックを運営していると、「またあのスタッフが休んでいる」と気になることがあると思います。
シフトが崩れ、他のスタッフへの負担も増えるため、管理者としては不安や不満を抱きやすい状況です。
ただ、感情的に注意したり、無視してしまったりすると、関係性がこじれたり退職につながることも。
今回は「休みがちなスタッフ」に対して、どのような姿勢で接し、どう関わっていくべきかを整理していきます。
「なぜ休みがちなのか?」の背景を探る
まず最初に大切なのは、「なぜそのスタッフは休みがちなのか?」という視点を持つことです。
よくある背景としては以下のようなものがあります:
- 体調が慢性的に安定しない(持病・メンタル不調など)
- 家庭の事情(育児、介護、パートナーの不調など)
- 職場への不安やストレス(人間関係、仕事への自信など)
- 単なるルーズさ、責任感の欠如
もちろん、本人から正直に理由を話してもらえるとは限りませんが、「何か事情があるかもしれない」という前提で向き合う姿勢は、信頼関係を築くうえでも大切です。
急に叱るのではなく、「対話」を重ねる
よくある対応ミスは、欠勤が重なったタイミングで「いきなり叱る」ことです。
これは本人の防衛反応を強め、「責められている」と感じさせてしまいます。
まずは1on1の場などで落ち着いて話せる機会を設けましょう。
その際のポイントは次の3つです:
- 事実ベースで話す:「今月3回のお休みがありましたね」
- 心配している姿勢を見せる:「何か困っていることがあるなら話してもらって大丈夫ですよ」
- 一緒に解決策を考える:「シフトの調整や業務の見直しでできることがあれば協力します」
「何とか出てこさせるための交渉」ではなく、「どうすればお互いにとって健全な勤務環境になるか」を探る姿勢が大切です。
他のスタッフへの影響を考慮する
一方で、他のスタッフから見て「休んでも許される雰囲気」が広がってしまうと、職場全体の規律が崩れます。
そのためにも、個別対応は個別に行うことが原則です。
休みがちなスタッフへの対応や配慮については、周囲にオープンにする必要はありません。
ただし、あまりに欠勤頻度が高く、フォロー体制が必要な場合は、リーダーやごく限られたメンバーにだけ説明するのも一つの方法です。
注意や改善要請が必要なケース
繰り返しの欠勤に理由が見えず、業務への影響が明らかになってきた場合は、「改善指導」も必要です。
その際には、以下の流れを踏むと効果的です:
- まずは個別面談で本人の意思を確認する
→「今後も安定して出勤できそうですか?」 - 業務上の問題点を明確に伝える
→「このままだとシフト運営に支障が出ています」 - 改善に向けた提案・約束を共有する
→「今後は急なお休みの前に必ず連絡を」「週◯回までにおさえる」など
このように「合意を取りながら改善に向かう」姿勢をとることで、単なる叱責ではなく建設的な対話にできます。
それでも改善が見られないときは?
最終的に、欠勤状況が改善されず、他のスタッフや業務全体への悪影響が大きくなってしまった場合は、配置転換や雇用継続の見直しを検討することもやむを得ません。
ただし、感情的な判断ではなく、「これまでに何度も対話し、改善の機会を提供した」というプロセスの記録が非常に重要です。
可能であれば、「改善指導書」や「勤務状況の確認書」などを活用し、やりとりを文書化しておくことで、本人にも現実を客観的に示すことができます。
まとめ
休みがちなスタッフに対しては、「仕方ない」とあきらめたり、「厳しくすれば治る」と考えるのではなく、まずは背景への理解と対話をベースに対応することが求められます。
一人のスタッフへの対応が、クリニック全体の風土に影響します。
だからこそ、やさしさと公正さの両立が、リーダーとしての腕の見せどころなのです。
スタッフとの信頼関係を維持しながら、安定した組織運営につなげていきましょう。
患者対応はまず【基本】を押さえることが大切です
▶接遇5原則 チェックシート活用法(全3回)を見る
▶電話対応 基本から応用/極意まで(全3回)を見る
無料リソースのご案内
スタッフの育成・患者対応は大事だなとお考えの医院には、
「接遇5原則チェックシート)」・BSCチェックリスト(75%公開版)を無料提供しております。
ぜひ下記からご活用ください。
グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。
先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。
接遇5原則チェックシート
接遇の基準をシンプルに可視化。
院内研修や個別指導に活用
満足度調査ツール 半年無料
満足度と改善点を数値化できる
E-Pサーベイが半年無料
BSCチェックリスト
医業収入UPの戦略マップづくりに
無料でも75%公開してます